本の紹介(3)
『劇場の神様』(原田宗典)2002年(新潮社)
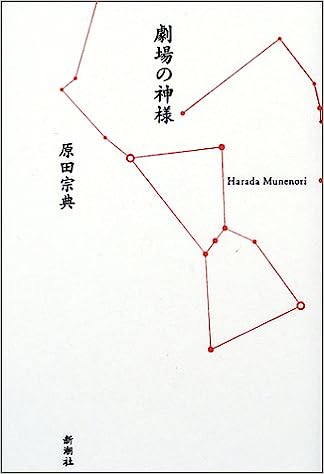
4編の短編集。本ブログが舞台に特化していることから、ここではその内の1編『劇場の神様』にだけ言及する。
手癖の悪い一郎は、度々の悪行から母親にも見放され、流れ着いたのが役者のまねごと。下っ端として大御所・近藤幸夫ショーに出演することになった。一郎は劇場に入るたびに、楽屋口にある神棚「劇場の神様」に手を合わせる。この姿を周囲に見てもらいたいという下心もないわけではないが、神様にお願いするのは「(自分が)どうか盗みませんように」そして「盗んでもバレませんように」の二つであった。…前者は分かるとして、後者の願い事も一緒に祈ってしまうあたり、一郎のダメ人間ぶりがわかるというものだ。その一郎が、とある「大御所風」を装う嫌味な役者の鼻を明かすため、その男の腕時計(偽物のローレックスなのだが)を盗むことにして、そしてその罪を、実力はあるのに手癖の悪さから落ちぶれた役者になすりつけることに決める。
決行は芝居本番中。一郎の頭の中で窃盗シミュレーションが明かされているので、読者も一郎がどうするつもりなのか分かる。そこに芝居『丹下左膳』の進行が重なる。しかもちょうどそのステージは「劇場の神様が降りて」きており、怖いほどに芝居の全てが上手くいっている――役者たちの高揚感、観客の興奮、調子が良いがために芝居のテンポも良くいつもより早く進んでいる…。
偽ローレックス窃盗事件と一郎がどうなるかは読んでのお楽しみとして、ここでは「劇場の神様」について触れることにしたい。「劇場の神様が降臨した時の芝居」、このビリビリとした興奮と緊張は、私にも覚えがある。もちろん私は観客側。これまで数千本の舞台を見てきたが「劇場の神様が降臨していたのだな」と後から振り返って思い出すのは1本だけだ。予定に含まれているカーテンコールや、千秋楽の達成感や興奮などとは明らかに違う、奇跡のような一夜。思い込みだと笑う勿れ、舞台に立っている彼らと客席にいる観客とが一体化してその舞台の世界にいた。終わりたくない、終わってほしくない、この世界に居続けたいという(全ての者の)思いが劇場に蔓延していた。そして、すべてが終わった時の、「ごおお」という大きな音。歓声とは違う、あれは何の音だったのだろう。
…そんなことを思い出しながらの本作。
本編で、劇場の神様が降りたつ芝居の片鱗を味わってみるのもいいかもしれない。


