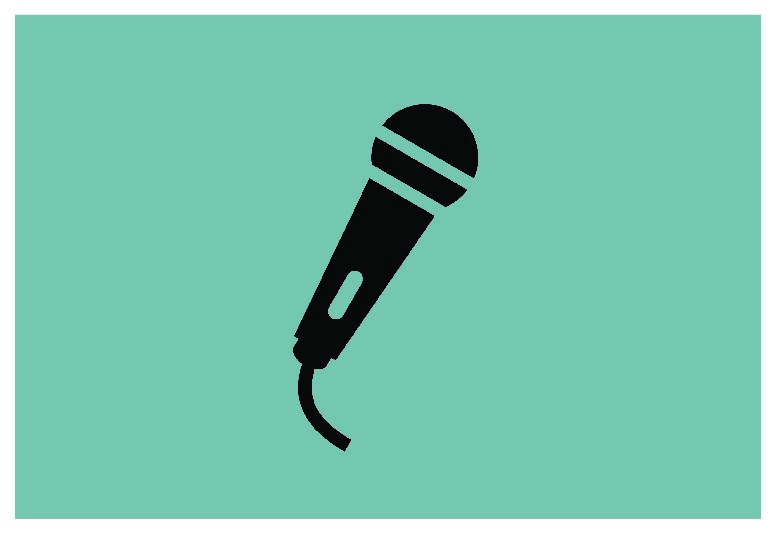2025年7月6日(日)16:00~17:30 @久留米シティプラザ スタジオ3
対象作品『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi(作・演出:菅原直樹、出演:粟井美津代、植月尚子、内田京子、内田一也、金定和沙、申瑞季、杉本愛、竹上康成、種原大悟、中島清廉、西春華、吉田省吾、岡田忠雄)
*2016年から福岡、小倉、久留米などにおいて不定期に「シアターカフェ」を開催してきた。シアターカフェとは、観劇した後に有志の観客(10名程度)でお茶を飲みながら、見たばかりの作品について語るというものだ。作品の役者・劇作家・演出家が参加してくれることも多く、毎回かなりの盛り上がりを見せる。
*私が初めて「老いと演劇」OiBokkeShiの存在を知ったのは2017年「全国シニア演劇大会」で菅原直樹さんの講演を聞いた時だった。その考え方、深刻で重大なテーマと作品の明るさの組み合わせ、演劇である意味…とても面白く聞いて、その日以来、いつか生で作品を見たいと願っていた。同じようにOiBokkeShiに関心を持つ方も多かったようで(テーマの吸引力もあったのだろう)、今回のシアターカフェは定員を上回る予約をもらい、飛び入り参加をお断りしたほど。いろんな立場の11名の皆さんとあれこれ話す、その楽しさよ…! 出演者(吉田省吾さん、申瑞季さん)も加わって、笑って、納得して、しんみりして、驚いて…。多様な人でつくり上げた本作を、多様な人たちと多様な視点で語り合う、いい時間になった。(わかりやすいように吉田・申さんのお二人の言葉は違う色で掲載してます)
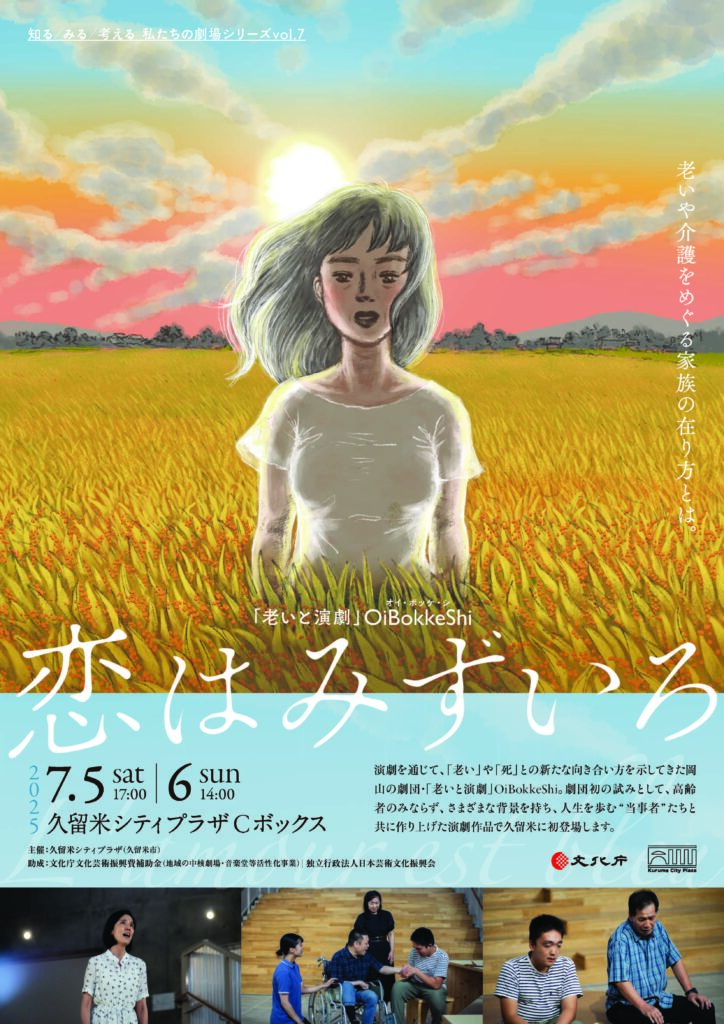
*文中の「オレンジ色の人物名」は、作品の登場人物名です。また、文章の流れの都合上、すべての発言を掲載したわけではないことをお断りしておきます。
●自己紹介と心に残ったシーンや言葉
みぃ:最後の政雄さんのシーンが心に残った。私には3人の息子がいて、それぞれが独り立ちしていく最中にモヤモヤしていることが、芝居を見て「こういうことだったんだ!」とすっきりした。泣けて。見られてよかったと思った。
えくぼ:笑いを届けるメルヘン介護士。菅原さんとは10年近く前にOiBokkeShiがたちあがるまえに縁があってお近づきになった。『恋はみずいろ』は、水色だけではない様々な色模様、人間模様があって、水色の中にみんな和解して最後は水に流そうじゃないかと捉えて、わだかまりを水に流せたのではないかと感じた。
ペンギン:菅原さんのWSに2回参加したことがあり、でも芝居を観るのは初めて。NHKに『ファミリーヒストリー』という番組があるが、一般人の我々にも記録されていないファミリーヒストリー、同じぐらいドラマティックなヒストリーがあったはず。父と母がいなければ私という存在はいない。父も母も大河ドラマのヒーローとヒロイン、そして代が代わって私が大河ドラマの主人公なのだと思う。地球上に何十億の大河ドラマが再生されていて、それぞれに主演しているのだと思った。
さこう:記者。2年前に菅原さんのWSに参加した。岡田さんの迫真の演技もよかったが、「この社会はウソかもしれない、だから今この瞬間を」というのが刺さった。この瞬間の積み重ねが人生なんだなと。
りえこ:「家族の関係は変わらない、変えられないんだ」というのが残った。ついつい家族だからと一線を越えて言ってしまう。個人、相手を尊重していかねばと思った。
なお:人にはいろんな面がある。母であり娘であり一人の女性であり。そのすべてがあってその人だが、年齢を重ねてそのどれかが消えてもその人はその人であると思った。99歳(岡田さん)元気がいい…。
ひーさん:行政で文化を担当していた。福祉と文化の関係性に興味がある。6~7年前に菅原さんのWSに参加して、本も買った。その時から菅原さんは変わらずぶれていない。
きんじ:福岡福祉向上員会をやっている。2年前に菅原さんを呼んで福岡市でWSをやってもらった。その時から芝居を観たかった。介護と演劇の親和性を知らせていきたいと思い、そんなWSもやりたいなと思っている。コミュニティカフェをやっている。最初から涙があふれそうになりながら観劇した。
よしえ:女優。去年、自分より20も上の79歳の役を演じた。自分の老いに向き合うようだった。だから今日の芝居も入所者側で見るのかと思ったが、佐代子さん(入所者の娘、50代?)という、今からいよいよ親が老いていく立場になって、芝居を見た。
あかり:医学部の6年生。高校から演劇を続けている。医療と介護と福祉とをテーマに扱った演劇にとりくみたくて劇団を立ち上げた。OiBokkeShiは大先輩と思って見に来た。本作では医療や介護が縦割りではなく一緒くた。キャストにハンディキャップがあってもそれでいいというお客さんと役者の関係が出来ていた。ハンディキャップがあっても、いい意味で「どうでもいい」というのが良いと思った。
佐野:以前、介護病棟で仕事したことがある。だがその経験から見たというよりも、自分と親の関係、自分と娘の関係に気持ちが持っていかれた。
やまちゃん:「介護」という言葉に引っ掛かって見に来た。両親が高齢、きれいごとは通用しない。ヒントがもらえたらと思って見に来た。岡田さんの生き様にも関心を持った。

●「この世界はウソかもしれないけれど…」
柴山:今の話を聞いていて、①作品の内容と離れて「介護と演劇」という観点での話 ②人間一人ひとりの生き様・在り方の話 ③家族の話 の3つに関心が集約できるかと思う。(出演者の)吉田さんも参加しているので(彼が演じる古千谷の)「この世界はウソかもしれないけれど、どうやったら本当の瞬間をつかめるか」というセリフについて話を始めたい。
さこう:嘘と本当は区別がつかない。区別の意味があるのか? 認知症とか関係なく。その人が「本当」と言えば本当だし。
柴山:ただ古千谷さん、うさんくさいなぁーと(笑)。
一同:(笑)
よしえ:前職が屋根(修理)というのが、もう絶対うさんくさいと(笑)。
吉田:屋根、うさんくさいですか!?
きんじ:修理が必要と言って近づいて…(笑)

柴山:シロアリと屋根修繕が、詐欺が近づく手口としてよく聞きますから(笑)。さこうさんはこのセリフにびびっと来たわけですが、他の方は?
えくぼ:グループホームで介護の仕事をしていると、普段は嘘八百。認知症のお年寄りの話に付き合うが、それはその人の世界に「お邪魔する」感じ。
柴山:その人にとってはウソではない。
えくぼ:こっちの世界に引きずりこもうとか頭ごなしに言うと、平行線。
柴山:先日の菅原さんのWSでは、認知症の方の世界に入り共有する、その瞬間その瞬間を「生きる」というのが演劇と介護の世界が似ているとおっしゃっていた。
●よりそう、さらけだす、信頼する
佐野:看護師なのだが、「笑顔」を作って入る。信頼を得る…そこまで言えないけれど、その人に「よりそう」とはどういうことかと思いながら仕事をしていた。
ぺんぎん:「よりそう」という言葉が今は安っぽくなっていて…
柴山:「よりそう」…家族の場合は難しい。作品の中でテルコの娘(増渕美鈴)はどうしても母親に優しくできないわけですよね、「私は他人だったら優しくできたのかな」というセリフがあった。家族は難しいのに他人だから優しくできる…。
えくぼ:仕事でも家でも介護しているが、家ではケンカ。血が濃いほどぶつかる。
りえこ:子どもは空想の世界を持つけれど、それと似ているのかと思った。自分は現実主義でその世界を共感できない。もっと頭を柔らかくしないといけないのかと…。
柴山:空想の世界にいながらも、人として人(他人)を信用することはできる。それは…なんだろう? 違う空間・時間軸の中に生きていながらも、古千谷さんに通帳と印鑑を預けてしまうほどに信頼する…。
よしえ:作品の中で「目と目を合わせて話す、これがすべて」というセリフがったが、認知症があっても見て話すことに何かが感じられる、そこが最後の一線なのではと感じた。
みぃ:でも通帳預かるとかありえない!と思った(笑)。

ペンギン:古千谷さんってホストの素質あるな!
一同:ああ~!
吉田:やってみたいなと思いますけど(笑)。
きんじ:人は承認されると相手との距離を近く感じる。詐欺師は言葉と態度でそうやって近づく。高齢者であり障がい者である人も、自分を認めてくれる人に対しては自分をさらけ出してくれる。信頼関係の築き方として大切。分かった上で演じなきゃいけない…自分を演じること、強い自分や優しい自分や…演劇みたいなものだと。
柴山:「さらけだす」…認めてくれたらさらけ出せる。ラストに正雄さんがそこにいない若い時の娘にむかって「行かないでくれ」と叫ぶシーンがあったが、あれは父親が娘に言えなかったってことで、今になってさらけ出しているってこと?
あかり:それより、松村先生のさらけ出し方について気になった。脳梗塞になったという設定だが、彼にとって何かきっかけがあってさらけ出せたのか。病気によってハンディを負って周囲からの助けによって人を信頼するのもあってさらけ出せるようになった…のなら素敵だと思った。
ペンギン:ブレーキが壊れたと解釈した。それまで抑えていた自分が。
あかり:病気によって?
よしえ:でも小説家になりたかったってセリフがあったから、元々表現したい人だったんじゃないかと。なんらかのブレーキがかかったのか表現の仕方が分からなかったのかもしれないけれど、元々はあったんじゃないかと。
柴山:素敵なラブレターを書いたようだし。
よしえ:うん。本当は表現したいことがたくさんあった人だったんだろうなと。全く違う人になったんじゃなくて、(元から)あった。
柴山:病気によって今までの通り伝えられなくなったから「伝えたい」思いが強くなったのもあるかとも思う。
あかり:必然性。
やまちゃん:その松村先生が一番印象に残っている。彼は子どもに戻ったんだと思っている。子どもの時は誰もがあんな感じなのに、大人になったら「あれしちゃだめ」と制約されていく。
柴山:例えば…由一くんも抑えて抑えて…大人にならざるを得なかった。そこに結び付く?
やまちゃん:がちがちに拘束されて。それが外れれば…そっちの方が人生が楽しいと思う。
みぃ:(舞台の)グループホーム青空のスタッフたちがにこやかで優しいから松村先生がああいう風になれたのかなと。私は支援学校で副担をしているが、担任が笑顔だと子どもたちも笑顔になる。
えくぼ:松村先生は子どもに戻ったことで、冒頭シーンの女子中学生が見えた…。だから30年経って会えた…。
見学していた出演者の申瑞季さん:すみません、横からですが…松村先生は台本ではあんな明るい役ではないと私は思ったんです。でも(内田)一也さんが演じることでどんどん天真爛漫に明るい役になって…。

OiBokkeShiの芝居は最初から完成形があるのではなく稽古場でその人の特性を生かしながら生まれた軌跡(奇跡)を物語にしていると思っています。
よしえ:松村先生は、時々かなりはっきりと喋ることがあって、だから一瞬、「この人は演技で(喋るのが困難な役を)やってる?」と思った。時々ものすごくちゃんとした活舌で。
ペンギン:間違ってもそれが正しい脚本だと思って進んでいくような演劇なんだろうな。
ひーさん:OiBokkeShiは全員アマチュア?
申:私と、もう一人北まりえ役(金定和沙)はプロです。
よしえ:演劇経験がある人は?
吉田:このメンバーは一人もいないです。
●演劇と介護――演劇の効用
柴山:作品の内容ではなく、「演劇と介護」という点について関心を持った方もいる。
あかり:医療の観点から言うと、「わからないこと」はたくさんある。病状説明も「わかったような、わからないような」で進んでいく方が多い。情報を自分事として受け止められているのか、疑問を持っている。私が考える演劇の効用として1つあるのは「演劇は狭くて深い」ということ。限られた人数だが心に届けられる。今日の芝居もそうで、介護施設のエントランスでの風景、表面上の会話は介護施設の話だが、そのレイヤーは上にあるけれどその下にあるのは家族の話。だから伝えたいことが自然と伝わる、それが私の考える演劇の効用。
柴山:「演劇の効用」という言葉が独り歩きするのは問題かと思っている。効用を目指しての演劇ではなく、演劇をやることによって良いことが出た、という順番がいいのだと思っている。
きんじ:先ほどのえくぼさんが介護中に相手の世界に入る話をしたが、認知症の方がいろんな時代や場所に行くけれど、それを外から見るのではなく一緒に行くことで向こうは安心する。自分と同じ世界にいるというのを感じてくれることでコミュニケーションがしっかりとれる。「演劇の効用」という言葉で片付けてはいけないが、そういうところもある。

よしえ:介護している時は「こちら側から(相手の)世界に入っていく」。でもお芝居は物語があるから、勝手にその世界に入ってしまう。介護の現場では、少し演技をして「入っていく」。でも今日の私たちは客席で見ていて勝手に誰かに…入っていく。「効用」という言葉は使いたくないが、そうやって入ってしまうのがお芝居だ。特に本作は群像劇の側面があるから、私が「佐代子」に肩入れして見たように、皆さんがそれぞれ誰かに重きを置いて見てしまう。「自分から入っていく」と「勝手に入ってしまう」は違うかなと思う。
●「個」の物語
柴山:個人の話という観点をあげている人がいたが、私自身も、今回の作品は個々人の成長…いや、「うまくできるようになる」という意味での成長ではなくて…変化、変化の物語かなと思った。例えば佐代子も父親に認めてほしかった。何者かになりたいという…彼女はそれでもがいていた。佐代子の父・正雄も最後の最後に「行かないでくれ…」と目の前にいない娘にむかって言うシーンがあるが、あれも娘が若い時には言えなかった本音を言葉にしていたという変化。息子の由一も母に「僕のお母さんでいてよ」と言えた。テルコの娘にしても母との接し方について考えようというセリフを残した。だからそれぞれの個人の…人はきっかけがあれば変われるし、変わりたいと思えば変われるし、変わらなきゃいけないかもしれない…という話かと思った。家族の物語でもあるけれど、一人一人の個人の話、とも受け取った。

●介護する/される
ペンギン:介護する側の覚悟は少なからず持っていて知識もあって覚悟もあるかもしれないが、介護をされる側の覚悟は実はない人が多い。介護セミナーなどの講師ですら、される側になることを考えていなかったり覚悟がなかったりする。そして介護される側の手記もほとんどない。それを考えると気持ちがよどむ。どうやって受け入れればいいのか…、そういうことを描いた劇があればいいと思うが…見るのも覚悟がいるけれど。
柴山:父が他界するちょっと前に、入院していて私に「もう帰りなさい」と言ったことがあって、理由を聞くと「病院では人にやってもらわねばならないことばかりで、つらい」と。その姿を見せたくなかったのだろうとその時初めて「介護・看護される側」のことを考えた。
よしえ:(劇中の)娘がお母さんに対して親だから優しくできないという話とちょうど逆。親側から見たら、他人なら仕事として頼めるけれど、と。
みぃ:私は任せられる気がする。1,2度だけシモの世話をしたことがあって、される側は受け入れるしかないのだと考えた。その時に満足いかない場合も含めて、自分の人生なのだと。
申:よく考えたら、お世話をする側、される側というのが(OiBokkeShiには)ないんです。あいまい。

吉田:お互いが助けてあげないとできないことがある時は助けられることをやるし、目に見えない形でこちらも助けられるし…お互い自覚していますし、「私が助ける人/あなたは助けられる人」ではなく流動的。
申:助けられてばかりいる人は、それはそれで大変。
なお:日常的にも国語が得意だから教えてあげる、ハンディキャップに限らず相手に対してどれだけ優しくなれるかってことだと。今日の公演も、そういうことが揃っている出演者だったり観客だったり暖かい空間だと思った。
ペンギン:目に見えない障がいに対しては…どうしたらいいんだろう。気にしない方がいいのかな。
申:時間はかかりますよね。障がいがありますと最初に言っちゃうと…
きんじ:最初からフィルターがかかると…。一也さん個人のつながりと(考えた方がいい)。友達もそうで、○○の病気を持っている誰、ではなく誰々が病気を持っている、という。
申:そうですね。
きんじ:関心を持つ、ことが大切。
申:自分発信でセリフを言うことにすごく一生懸命になってしまうけど、どう相手のセリフを聞くかが大事かなと最近思います。
よしえ:演劇経験者が少ないとのことだが、根気強くお互いのことを訊こうとしているなというのが伝わってくるお芝居で、それは上手い/下手ではなく、対人間、ちゃんと向き合っている。ちゃんと向き合って、その人のことを聞いてやろうとする。それは演劇の上で当たり前のことなんだけど、それを根気強くやろうとしている演劇だなと。とても基本的なことをちゃんとしていると思った。
●歌
ひーさん:台本についての感想だけれど、中学生二人のシーンが重い話の中での清涼剤だった。もう一つ、役者が舞台からはける時にセリフを言いながらだったのが印象的。
よしえ:そう、中学生のシーンがエモくて。清涼剤といえば、最後の彼女(申さん)の歌。本当に。あの声でどっと涙が出ました。浄化してくれる感じで。
柴山:「あなたにすべての花をあげる、あなたにすべての光をあげる」という歌詞、あれが…基本だなと思った。「人に優しくする」という言葉ではなく、その心根にある、きれいなものを見た時に見せたい、あげたい、という気持ち。それがストンと胸に入ってきた。
申:あの歌は、菅原さんから『恋はみずいろ』を歌ってくださいといわれたんですけど、著作権があるから似た歌を作って歌ってくださいと言われて、歌詞は私が書きました。普通の演劇ではなくてOiBokkeShiのように少しでも役に立てるところで演劇を命と元気をもらいながらさせてもらっています。もらうよりあげたいという気持ちの方が強くなって…
柴山:だからあの歌詞…
申:そうなんです。あの言葉が空から降ってきて。(息子役の)由一にすべてをささげたいと思ったんです。…芝居の時に、花と光をあげたいと思ったんです。
ペンギン:そうか、なぜここで『恋はみずいろ』を歌わないのかなと思ったが…。OiBokkeShiには伝説のロックバンドQueenの『I was born to love you』をモチーフに芝居を作ってほしい。その中の歌詞で、I was born to take care of you.というのがあって、ケアするために生まれた――日本語でのケアは介護のケアと思うけれど、英語は「守る」というニュアンスに近いと。介護の「護」とは守るという意味。身体を張って守る。だからOiBokkeShiに、そのテーマで…菅原さんに言ってください。
吉田:はい…。余談ですが、一昨日入った屋台の店主が、フレディ・マーキュリーに似てました。
一同:(笑)

申さん:(ここで退出)いつもだったらお芝居終わってすぐ帰るんですが、こんないい時間が持てて宝物にします、ありがとうございます。
柴山:ちょうど1時間半になったので閉めたいが、最後に何か。
やまちゃん:吉田さん、演劇経験なく入ったわけですよね、OiBokkeShiに入る前と入った後での変化は?
吉田:OiBokkeShiはそこにいるメンバーと日々WSをする中で脚本が出来ていくんですよ。脚本をもとにメンバーを集めるわけではない。いるメンバーから脚本ができていく。こういうところを見られているんだなとか、菅原さんからこう見えてるんだなとか。
よしえ:胡散臭い役が…(笑)
一同:(笑)
吉田:そうなんですよ! 自分でも思っていた姿も含まれてますが、意識しなかった部分が含まれていて。だからたぶんね、我々のためにまずこの演劇はある。これをやる演劇をやる我々が楽しい、楽しいだけじゃなく苦しい。それをごちゃごちゃ味わう演劇…見るのももちろんいいんですけど、自分が何かをやるということを発信しているのかも。パンクですね。パンクって3コードで出来るから「俺でもできるかも」って若者がガーってやったんです。だから見た後にやりたいという人が来る。
一同:ああ…!
やまちゃん:失礼ですがおいくつですか?
吉田:39です。明後日が誕生日です。
一同:おお~おめでとうございます…! (と拍手)
吉田:見つめ直すことになりますね。81歳の友達がいるんですけど、よくあちこち一緒に行くんですけど、一人ではたぶん無理だから僕が段取りしてこの間もロシアに一緒に行って。
一同:え~。そりゃ印鑑預けたくなるわな…(笑)
吉田:僕もことさらその話をしていたわけじゃないですけど、たぶんその話も(菅原さんに)嗅ぎ取られていたんでしょうね。
柴山:40歳もの年の差があっても「友達」って言えるところがいいなぁ!
<ここで菅原さん、登場>

武田有史さん(サポートスタッフ兼出演も)、竹上康成さん(津元美智雄役)、武田知也さん(制作 bench)
柴山:今、終わろうかというところでのご登場! ありがとうございます。いろんな話が出ました。演劇と介護、人としての話、家族の話など。吉田さんや申さんにもお話を伺って「お互いがお互いをサポートする」話をしました。
ペンギン:観客の方も満足したと思うけれど、吉田さんや申さんもこの会で一緒に話せて、割増料金があってもいいほどで(笑)。ただ見て帰るのとここで話すと受け止め方も深みが出るし、良かったです。ありがとうございました。
よしえ:全然、関係ないこと言っていいですか。松村先生と彼(その場に来ていた中学時代の松村先生役の種原大悟さん)がすごい似ていて、顔立ちが。すごい納得したんですよ。映画でもよくあるじゃないですか、子役が微妙に似てて納得する。彼が後半にしか出てこないけど出て来た時に「ああ、間違いない!」って(笑)。さっき部屋に入ってきた時にこれは言いたいと思って(笑)。
柴山:あのシーン、中学生同士のシーンについて、清涼剤という声がありました。清涼剤というだけでなく、お互いに一人の人間として認めあうシーンじゃないですか、それがあったから「自分は何かになっていきたい」と佐代子は思った。だから親ともぶつかるんだけど、あのシーンが一つの軸になっていて大切だと思いました。
えくぼ:この作品は何かモチーフになったものがあるんですか。
菅原:これはOiBokkeShiの集大成と言ってるんですけど、『老人ハイスクール』という作品を以前作ったんですけどそれは高校が廃校になって老人ホームになった。その要素もちょっと入っています。それと「何者にもなれない人」を描くというのもOiBokkeShiがやってきたことなので、今まで10年間やってきたことがちょっとずつモチーフが重なって、そこに奈義町の方だったり大学生だったりの個性が入ってこうなりました。
柴山:質問していいですか? おかじい(岡田忠雄さん)が出演なさらない可能性もあったわけですよね? その場合はどう終わる予定だったんですか?
菅原:台本は中学生のシーンで終わるんです。
一同:えー!
菅原:お母さん(佐代子)はやってこない。由一がふり向いていて、中学生が去っていく、でお終いだった。それが僕が書いた台本だった。
柴山:では歌もなかったということですか。
菅原:歌も入ってない。お母さんも現れない。で、おかじいも出ない。これは奈義で作って完結する作品なのですが、岡田さんは2時間ぐらい離れた所に住んでるので…ただ岡田さんの存在を感じさせるキャラクターは作ってたんです。でも最後、こういう形で。次の公演は鳥取の智頭でやるんですけど岡田さん出ないから…歌はあります。ピアノの生演奏があります。
ペンギン:あの歌は、リリースしてほしいね。
一同:うんうん(笑)。
菅原:それは…(まずは)クラウドファンディングで…(笑)! (おかじいのドキュメンタリー映画のクラウドファンディング実施中です!)