山下晶さん(俳優・作家・演出家/グレコローマンスタイル)
*グレコ(グレコローマンスタイル)の作品、私好きだったんですよね~。遊び心があって。選挙の話の時はチラシが選挙ポスターだったり、プロレスの話の時は舞台上に大きなリングが登場していたり。『スピーカー』という作品が面白かったのも記憶しています。そして、山下晶という役者もまた、とても印象深い存在です。様々な役を演じているけれど、特に私は彼が舞台から客席の遠くをながめる姿が脳裏に焼き付いていて――グレコの作品でも、『水の駅』でも、『滑落、我ら大八食産登山部』でも――、大きな体いっぱいに哀しみを湛えている演技などは惹きつけられます。いまでは俳優、作家、演出家としてだけでなく、韓国と福岡を演劇でつなぐ活動もやられていますが、それもこれも山下さんの人柄のなせる業でしょうね! 色々と赤裸々に語っていただきました。

インタビュー
柴山:お芝居を始めたのはいつ頃ですか。
山下:高校演劇も大学演劇もかじってなくて。もともと料理人になろうと思っていて、熊本で大学を中退した後に…フランスに行きたくてお金を貯めていたんですよ。その時にCMに出て見ないかという話がありまして、今より痩せてたんで(笑)、ローカルのCМに何本か出てたんですよ。
柴山:芸能事務所に入ったわけではなく?
山下:違います。街でスカウトされたというか。地方…熊本とかちっさい所ではスタイリストさんがキャスティングしたりするんですよ。それで声をかけてもらって。それで何個か出るうちに佐藤さん(順一さん、演戯集団ばぁくう)と共演するんですよ。熊本で。ちょうどバブルが終わったようなころで、お金がちょっと残ってるから、事務所が福岡からタレントや役者を呼んでということをしていたんだと思うんです。
柴山:山下さんは事務所に所属されていたってことですか?
山下:いえ、フリーで。佐藤さんもCMで来て。何かやってるのと声かけられて、「本気でやる気があったら福岡出てきなよ」って。たぶん社交辞令だったと思うんです、でもそれで福岡に出てきたんです。
柴山:ではもう福岡でタレント、モデルをやろうと思って出てきたということですか。
山下:そうですね、ばぁくうをモデル事務所だと思っていました。いざ来てみたらめちゃくちゃ真面目な硬派な芝居をする(笑)。その時初めて別役実とかを知って。こういう世界があるんだと。入ってみたら「あ、モデル事務所じゃないんだ」と。でも…両親が公務員で、僕自身もパティシエになろうとしていてなんとなく人生設計ってできるじゃないですか。役者って言うのが全く今までにない世界で、田舎に住んでいたので、これは人として賭けてみるのも面白いかもしれないと思って。
柴山:それまでお芝居はご覧になったことは?
山下:両親が熊本市の職員なんですけど、市役所に人形劇団「たけのこ」というのがありまして、そこに二人とも入っていたんですよ。だからちっさい時から人形劇には触れてました。でももう、ずっと野球をしてましたし、文化系クラブなんかも「男がするもんじゃない」と思ってましたし。佐藤さんで初めてその世界を知った。
柴山:佐藤さんの所で「モデルしかやらない」という選択肢はなかったんですか。
山下:言葉を選ばずに言えばあそこも***みたいなものですから(笑)「モデルだけしたいです」なんてありえない。いつのまにか音響させられていたとかそんなところから始まって。ただ、本当に新しいことだったんで楽しくて仕方がなかったですね。
柴山:ばぁくうは事務所でありながら劇団ですよね、お金は劇団に収めていたんですか。
山下:払ってなかったですね。お仕事としてそこから%は引かれるので、団費みたいなものはなかったです。
柴山:お芝居を劇団でやりながら、タレント活動もされていたんですね。
山下:はい、今はこんなですけど(笑)若い頃は、見てくれも良くてお芝居もできるということで重宝がられて。東京に行かなかったのも、ある程度福岡で早いうちから隙間的なナレーションやCМに出て…もちろんアルバイトはしてたんですけど、やれるんじゃないかということで東京には興味がなかった。
柴山:当時はお芝居とモデルではどっちに重きがあったんですか。
山下:…お芝居というのがそこで初めて教わったので…でも当時はそこまでお芝居に入っている方じゃなかったです。どちらかというと目立ちたがり屋、テレビに出るとかモデルとかそういうことに興味を持っていたんだと思います。
柴山:では地方が作るテレビドラマなどもお出になっていた?
山下:ばぁくう時代はそこまで多くなかった。役者の仕事としては…金額ではなく役者の安売りみたいな意味で安いですけど、カラオケビデオの映像。あれが福岡で撮られてたんで。それで(自分が出ている歌を)持ち歌にしてたりとか。それで画角とか、撮られるとか、そういうことをすごく学んだ気がします。今で言うと「縦型」があるじゃないですか、あれは撮られることにすごい勉強になるんで、若い人たちはいいなぁって思います。「縦型」っていうのはTikTokとか、スマホで見るからわざと縦で撮るもののことですね。
柴山:ああそうか、映画なんかは横ですもんね。それはあくまでも画面ごしの話ですが、お芝居の空間にそれは役に立つんですか?
山下:それは…今つらつらと考えてどうして自分がお芝居をやってるんだろうっていうと、たぶんショーケースとしてこういう人がいますよとアピールツールとしてお芝居をやってきた気がします。今だったらスマホで自分で撮ってYouTubeにあげたりできますけどそういう時代でもなかったんで、こういう芝居をやってる人使ってみませんかとか、ナレーションもできますよ、とかツールとして使っていた気がします。それによってお芝居に活かされたかというとそれはなかったと思います。けっこう考え方は…ばぁくう、その後、坪内守と西田と3人で団体をやるんですけど、それもやめて自分でグレコローマンスタイルをやりますけど、その3段階でお芝居に対する考え方って全然違います。
柴山:ではばぁくう時代はあくまでも、アピールするためのツールだったということですか。
山下:ただ、最初に会ったのが佐藤さんだったので、「芝居って言うのはそんなに甘いものじゃない」という佐藤イズムは植え付けられたような気がします。
柴山:佐藤さんはお芝居に厳しくストイックな方だと聞いたことがあります。鍛えられたのでは?
山下:そう…ですね、僕は2年ぐらいしかいなかったんです。周りから言わせると僕にはすごくかわいがられて甘かったと。でも僕からしたらめちゃくちゃ厳しかったですよ。みんなで「今日こんなことがあったんですよ」なんて話すじゃないですか、そしたら「ふーん、そことそこのイントネーション違う」とか(笑)。仕事に対する思いとかはすごく厳しくなさってましたね。
柴山:佐藤さんも一生懸命に山下さんを育ててくださったんでしょうね。
山下:そうでしょうね…でも若かったんで、何もかも急にいやになってやめると言い出したんです。今となって見たら恩を仇で返すみたいな感じでやめた気がします。
柴山:2年ぐらいいた時はばぁくうのお芝居にお出になっていたんですよね。何本くらい?
山下:2本出たと思います。だいたい年1ぐらいでしたもんね。レイ・クーニーの『ラン・フォー・ユア・ワイフ』っていうのは少文(少年科学文化会館)で。もう一つはキャビンホールでしたかね。
柴山:やめたのは、突然だったんですか。
山下:一番仲の良かった坪内守がばぁくぅやめちゃったんですね、一言では言えない複雑な理由で。僕は一番仲良かったのに一人残されて、それもなんか若かったしそんなに簡単に切り捨てられるのも信じられなくて裏切られた気がして。それから半年後に次の作品は何をするかという話し合いがあったんです。稽古の初回日程を決める時に僕が友達の結婚式があるから出られませんと言ったら、佐藤さんが「お前が幸せじゃないのに人の幸せを祝っている場合か」って言われたんですよ。それで「佐藤さんにそんなこと言われる筋合いはないです」と言ったら、ピー(掲載不可)。…でもう、そこから半年ぐらいいたんですけど、もうやめることしか考えてなかった。若かったですね、ハハハ。
柴山:ばぁくうに入られたのはおいくつですか。
山下:22。
柴山:では24の時におやめになったんですね。そのあと作られた団体は。
山下:坪内守、西田優史と、「テストデパートメント」。劇団…これも笑い話なんですけど、佐藤さんは「劇団」という言い方を嫌っていたんですよ。それで劇団ではないなぁと何もつけずに「テストデパートメント」と。2カ月に1度ぐらいコントライブをしてました。ハイビームという場所で。
柴山:ああ、ハイビーム。あそこは一体何の場所なんでしょうか。
山下:えっとカメラマンの人、今ドキュメンタリー映画とかを撮ってるんですけどその人と坪内守が相談して作ったスペースですね。ライブもありましたしお芝居もやりましたし写真のスタジオにもなりましたし。
柴山:その時はタレントさんはやめていたんですか?
山下:いえいえやってました。でも一回全部、ばぁくうをやめる時にスパッと切って。携帯のない時代ですから連絡も取れず「あの子辞めたんだ」ぐらいで。たまたま知り合いとか元々繋がっていた人から声かけてもらう感じで、全然食べれなかったですね。
柴山:コントライブはどのくらいの集客があったんですか。
山下:3回公演するんですけど、多い時で全体で100ちょっと入ってました。コントとコントの間に、僕たちが出演している映像とかオープニング曲はその人が音楽もやってたんでそういう界隈の人とかを巻き込んで…。90年代ですね。
柴山:ちょっとおしゃれな感じで、先駆けだったのかな。
山下:そうですね、福岡ではあんまり見かけなかったんで、自分たちで言うのもアレですけど…僕らが先端という自負はありましたね。音楽と映像と劇場じゃないところでやるライブ感覚でする、扱っているのはお芝居じゃないけどコント…だけど設定も自分たちで考えていたし、映像も幕間に流すというのは福岡では見たことがなかった。面白いことをやってるんじゃないかなと思っていましたけど、東京や大阪ではやっていたことを後から知って井の中の蛙…俺ら福岡で一番みたいなこと言ってたけど足元にも及ばんかったと(笑)。
柴山:ではお客さんも若くてオシャレな感じ…アート系にアンテナ張ってるような方が多かったのかな。
山下:一般の人(普段お芝居見ないような観客層という意味)も多かったですけどね。逆に若い劇団員とかの方は見にきてませんでした。珍しい存在だったんじゃないかなと思います。
柴山:佐藤さんの所ではほぼ新劇のお芝居だと思います。テストデパートメントではコント。これは山下さんが書かれたんですか。
山下:いや、坪内守がほぼ。僕は1,2作しか書いてません。漫才みたいなのはあまりなかったですけど、シチュエーションとかにこだわったシチュエーションコメディ…とまではいかないけど、コントみたいな感じ。
柴山:どのくらいまで続けたんですか。
山下:2000年…25歳から30ぐらいまでの間…。2カ月に1回というのは最初の2年ぐらいでしたね。それからほかの二人がソロでそこで活動したりということもあったので。でもその時、僕はいじけタイムだったかもしれません(笑)。
柴山:いじけタイム?
山下:坪内守とかがソロでカメラマンの人と色々やっていたんで、あんまり…記憶がないですね…バイトをしていたかもしれないですね…。
柴山:いわゆるお芝居をやりたいということはなかったんですか?
山下:…んーなかったですね、たぶん。
柴山:30ぐらいまでお続けになって、そこからグレコ(グレコローマンスタイル)を作られたんですよね、その経緯は?
山下:「パブリックチャンネル」(タレント事務所)の1階に屋台風居酒屋ができたんですよ。そこで僕が働き出したんですよ。そこにたまたま西日本俳優協会(NHK)の岡本ヒロミツが来たんですよ。その時いじけタイムだったし、岡本君も自分の団体がどうかなぁということで二人で何か面白いことする?と。そこからですね。
柴山:パブリックチャンネルにはもう所属されていたんですか。その上で、1階の居酒屋でも働き始めた。
山下:はい。ソロ活動をみんなに知らせた時にパブリックチャンネルは坪内守しか所属していなかったんで、後に僕が入るんですけど。西田は「パインズ」っていう事務所に入りました。
柴山:ではその頃にはタレント事務所は増えていたということですか。
山下:ナベプロが来たのがけっこう大きかったです。今ほど多くはないですけど、ちょこちょこ増えてきた時代です。
柴山:タレント事務所って、そんなに仕事が来るものなんですか。
山下:そうですね…吉本が一手に担ってた時代があって、その時はいっぱい仕事があったと思うんですね。吉本の後に渡辺(ワタナベエンターテイメント)が来てからいろんな番組が増えてきたんですよ、リポーターとか、後はモデル事務所で。僕はちょうど芸人さんでもなく、タレントでもなく、ナレーションもやって役者もやってモデルみたいなこともしてと中途半端なところにいたので、その分周りをよく観察してました。(※このあたりのことは別の話で話せばムチャクチャ長くなります。割愛!)
柴山:グレコを結成したのは31歳?
山下:いえ、32です、2002年。
柴山:それはお芝居をするつもりで始めた?
山下:そうですね。
柴山:先ほど、「お芝居に対する山下さんの考え方が3つ(の所属団体)でぜんぜん違った」とおっしゃいましたけど、テストデパートメントの時はいわゆるお芝居は全くしなかった。でも岡本さんと会っていきなりお芝居をすることになった。そこはどういう?
山下:テストデパートメントの時が一番ショーケースというか「自分はここにいますよ」というのをアピールするためにやっていた。うければいいという感じで。そうじゃなくて自分がやりたいこと、表現したいことと考えた時に…。テストデパートメントでは坪内守がずっと書いていたんで、他に書く人がいるか、在り物をするか…と。実はこれもちょっとあって、ばぁくうが在り物の作品しかしないんですよ、絶対。それにも反発心もありました。自分でも面白いものが作れるんじゃないか、なるべくオリジナルでしたい。という時に、人がいないんで自分で書いて自分で演出して自分で出演するような団体を作ろうと二人で。一番初めのキャッチプレーズが「役者の役者による観客の為の演劇」でした。自分たちで面白いことを観客に見せる、ということで始めた。たぶん責任が違ったんじゃないですかね。テストデパートメントの時は坪内守に任せておけばいいと。
柴山:ではその時は書こうとは思ってなかったんですね。
山下:思ってないですね。…今でもそうですけど、役者が一番面白い。
柴山:書く事から始める、一から始めようと思われたわけですが、そこでコントに行かずにお芝居に行った理由は?
山下:単純にコントはやったし。実はその後にコントはやるんですけど、グレコで『売名旅行』っていうのを。
柴山:ああ、拝見しています。
山下:オムニバスでその間に映像が流れて。
柴山:テストデパートメントを踏襲した形だったわけですね。さて書くとお決めになって…
山下:僕と岡本で交互に1本書いて演出、もう一人は制作。2006年くらいまでそれの繰り返し。最初は『アタルモハッケ』ですけど僕が書いて、岡本が『灰色小浪漫』を書いて。これはあなぴとうちと大阪の自由派DNAという所がぽんプラザで日替わりで…。


柴山:見てます。失礼ながらあまり覚えてないんですが…色がテーマ?
山下:あなぴが(DNAかも)オレンジで、うちが灰色。「グレイ(灰色)/コ(小)/ローマン(浪漫)」で『灰色小浪漫』だったんですよ。僕は(岡本の)そういうのが好きなんですよ(笑)。
柴山:(笑)あ~あ! 基本的なことなんですけど、「グレコローマンスタイル」という劇団名の由来は?
山下:最初、領収書を書いてもらう時に書きにくいやつにしようやと(笑)「薔薇檸檬」とか(笑)。どんな字書くんですかと言われた時に自分たちも書けないという(笑)。それでその時、名前を付けるセンスのある知人がいて、「グレコ&ローマン」ってどうかと言われたんです、でも、「どっちがグレコ? どっちがローマン?」とか言われそうだったんで(笑)、シンプルに。僕はプロレスは知らなかったんですけど、調べてみると「フリースタイル」と「グレコローマンスタイル」というのがあって、グレコの方は下半身に触れてはいけないとか技は投げ技がいけないとか色々制約があって。芝居ってそうだなと思って。色々な制約の中でそれぞれの力を磨いていくみたいなところが。それでいいなぁと思って。後々に自分の団体検索しようとしたらアマレスのグレコローマンスタイルばかり出て来るんで、えらいことになるんですけど(笑)。
柴山:プロレスのお芝居もされましたよね。だから二人ともお好きなんだと思っていました。グレコ時代は年1回ぐらいの公演でしたっけ?

左より、岡本ヒロミツ、山下晶、筑前りょう太、めんたいキッド

山下:そうですね。カフェなんかでの小さいのはもう少しやってましたけど大きい公演となると年1ぐらいですね。
柴山:ここカフェソネスとかですよね。他にはどこを使われていました?
山下:昔、秀巧社があったビルの1階がスペースがあったんでそこでやっていたとか。日田にあるカフェとか。大牟田でもやったことがあります。
柴山:そういう小さなスペースでやっている時はお客さんの数が入らないからペイしないのではないかという気がするんですけどそうでもないんですか?
山下:僕らが単体で動いていたというよりも、カフェソネスだったら「カフェウィーク」っていうイベントがあったんですね。その一環として芝居をやるとか。手弁当でもいいから参加しようと。「テストデパートメント」の流れじゃないですけど劇団とかがしないような所で活動をやっていってもいいんじゃないかというのがありました。
柴山:カフェでやり始めたのはいつ頃からですか。
山下:考えたことない…
柴山:カフェでお芝居とかやるのが流行り出したというか、増えた時期があると思うんですけど、それはグレコのもうちょっと後かな。
山下:後だと思います。早すぎたって僕たち言ってましたもんね。
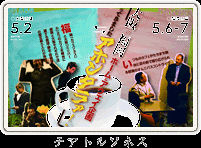
柴山:グレコで初めて脚本を書かれたわけですが、私はずっと面白く面白く拝見していました。…どのくらいまでグレコは活動されていたんですか。
山下:20014,5年ぐらいですね。『晴レタラ、見エル。』が最後ですね。ちょっと韓国とのやり取りに忙しくなって。

柴山:ハナロですか。
山下:そう…ですね。でも最初に個人で始めて、それからハナロ(プロジェクト)に加わるんですけど…。釜山のトタトガという…釜山の中央洞という所が昔は市役所があって栄えていたんですけど市役所が違うところに移って、周りの印刷所なんかも移ってゴーストタウンみたいになったのでそこをどうにかしようと釜山市が芸術家に安く貸すことにした、そういう活動の拠点がトタトガ。絵画や彫刻なんかの芸術とかは宮本初音さんの「ワタガタ」(韓国語のワッタガッタ=行ったり来たり)で交流があったけれども芝居は韓国も盛んだけど福岡との繋がりがなかった。それでだれか紹介してくれないかということでキム・ヒジンから僕の所に来たわけです。
柴山:どういう繋がりですか。
山下:いけだ世佳さんという、韓国人と結婚されていてもうお亡くなりになってるんですが、その方と僕は直接会ってなかったんですけど屋台の大将を通じてそういう人がいるということを知っていたんです。聞いていたんです。キム・ヒジンが「誰か知らない?」といけだ世佳さんに言って「一人知ってるから紹介する」って。ただ、キム・ヒジン(トタトガ)も福岡に誰かいないかと宮本初音さん経由で来たのが、「劇団Fourteen +」の中島さとさん。だからキム・ヒジンは両方に行ったんですね。トタトガ経由の話は今はサトさんの方が重点的にやっていて、僕は最初だけかじってそこから韓国の魅力にハマってハナロ(プロジェクト)に加わった。
柴山:韓国語がお出来になるんですか。
山下:いいえ。日本語しかできない(笑)。通訳が入りますけど…。僕何回か芝居をやめようかと思った時期があるんですよね。ちょうど2014年のちょっと前ぐらいに、九州のテレビ局で制作されるドラマがNHK福岡、NHK大分、FBS、TNC、RKBの5局ぐらいに一年で出たんですよ。東京とかで考えたら、普通に売れっ子でみんな知っている役者さん…なのになんーにも来なかったんです。今まで自分が目指していた頂点…こんな役者になりたいって思ってやってきてその頂点ぐらいだったんですよ、でも何も変わらなかった。
柴山:どんなふうに変わると思っていたんですか。
山下:多忙。売れっ子というか。お金も話もどんどん来るだろうし。でも地方の役者なんか誰も気に留めてないし、業界の人はもちろん認めてくれてますよ、でも何も変わらん、今までと。俺目指してきたものの上に来たのに何も変わらん、じゃ次何をめざせばいいのって。極論言えば東京行くしかない、お金を稼ぐなら。どうしたらいいんだろうという感じになったんです。そのときにたまたま話があって韓国に。もともと韓国の助成金を使って一週間ぐらい韓国に滞在して韓国の話を書いてくれということだったんですよ。それで一週間行ったんですよ、全然韓国語話せないけど。そしたら毎日宴会してくれた時にそんなことを言うじゃないですか、そしたら「いや、山下お前は何も間違えてないよ。やりたいことをやってるんだろ? それを卑下することは何もない」みたいなことを言われて僕はボロボロ泣いて。あ、何も間違ってなかったんだと。豊かではないけれど暮していける、これでいいんじゃないかと思わせてくれた。それで韓国との交流をやっているのは、そう思わせてくれた恩返し。グレコは今はちょっとやれてなくて…その後コロナも入ってくるんですけど、グレコより先に韓国とのつながりが。それとグレコのメンバーが東京行ったりいなくなっちゃって実質岡本と僕になって。ちょっときつくなって。何のために自分で書いてお金を出してやってるのかと。それで一回、グレコよりも韓国のことを。
柴山:ハナロプロジェクトというのは、プロジェクトという名称がついているので助成金をもらって数年間やる、ということかと思ってました。
山下:コロナでちょっと途絶えたんですけど。元々は2014,15年に同時多発的に釜山と福岡とのやりとりが4か所くらいでできたんですね。キム・ヒジンが僕と、さとさん。そしてキム・セイルが日下部君と一緒にやったのがハナロプロジェクト。そしてもう一つ山田さん(GIGA)が韓国とやった。
柴山:それで山下さんは今ハナロをやっている。
山下:そうですね、僕とキム・セイルと、酒瀬川真世と、それぐらいですね。
柴山:ハナロプロジェクトの最初は『百万ウォン…』でしたよね。
山下:その後に『ドラマ』をやって「一部屋の教会(作:日下部 信)」『セレモニー』、『ナ・チャレッチ』(作:幸田真洋)。最初は日本の戯曲を韓国語に訳して韓国の劇団がやる、韓国の戯曲を日本語に訳して日本の劇団がやる。2回目「ドラマ」が韓国製作の同じ脚本を日韓それぞれで演出。3回目の『一部屋の教会』は逆に日本の脚本を日韓でやる。2本目の『ドラマ』を僕が演出したんです。


柴山:2年ほど前の『水の駅』はキム・セイルさん演出でしたがあれもハナロじゃなかったですか?
山下:あれは2018年に釜山の市民劇団でセイルさんが演出したんです。それで手ごたえを感じて、どうしてもハナロと繋げたかったんで福岡でオーディションして配役を考えた。
柴山:あれは非常に面白かったですよね。失礼ながら場所がももちパレスの大ホールだったのでどんな感じだろうと思っていたんですけど、ひじょうに良かったです。
山下:賛否は別れましたけど。見慣れてない人から見たらなんのこっちゃわからないでしょうから(笑)。でもものすごく深くて。最初は沈黙劇って全く分からなかったですけど、これほどまでに伝わるものかと。様式美、歌舞伎みたいなものですよね。

The Water Station, InlanDimensions International Arts Festival 2022, photo by Tobiasz Papuczys
柴山:グレコの話に戻れば、団員も少なくなってしまったから今は休止、と。やめたわけではなく。
山下:ただ、2002年に旗揚げなので20周年はうっかりして忘れてましたから(笑)、次25周年で来年ぐらい何かしたいねという話はしています。昔のリバイバルとか。重い腰でも挙げてみようかという話はしています。
柴山:昔ハイビームでやった『スピーカー』、あれめっちゃ面白かったと記憶しています。
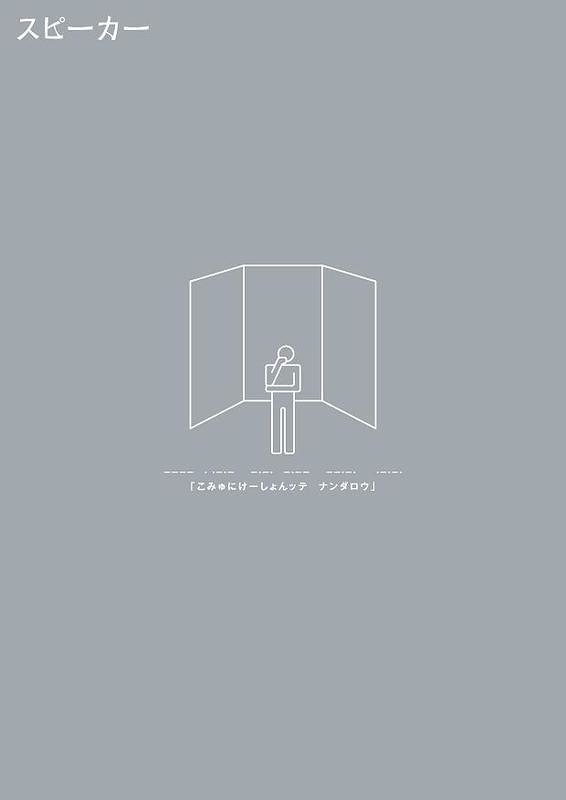
山下:補足すると、グレコを立ち上げる前に『12人の怒れる男たち』をやりたい、そのための資金を集めるために権藤昌弘(西日本俳優協会)河原新一(轍WaDaChi)の3人でやった版の『エンドレススピーカー』をご覧になってると思います。最初はテストデパートメント時代に坪内守、西田優史の3人でやりました。
柴山:ハナロの方は。
山下:『セレモニー』は何回か再演しているんですけど、釜山の通信使のお祭りでやったし、あれは船上結婚式の話なので本当に船上でやってみようという企画があってそれも出たんですね。クルーズ船なので本当はマジックショーとか歌謡ショーとかやる時間のために1時間半を50分に短縮してやったんですけど色々と課題も残る…。でも今年それを福岡と釜山で再演しないかという話が出ています。
柴山:お金はどうなっているのですか。
山下:日本はある程度、集客を見込んで予算立てするんですけど、韓国は助成金頼りなんです。だから助成金が取れなかったらなくなるかもしれないですね。僕たちも助成金をいくつか出してみて、取れたらありがたいねと。
柴山:では基本的にハナロプロジェクトは助成金で続けられた?
山下:運よく日本の助成金がとれてきたのが大きいかもしれません。韓国が、政治がらみもあって、対日本一か国だと助成金がおりにくいらしいです。三か国ぐらいと一緒じゃないとおりにくいみたいです。でもハナロの主旨が「韓国と日本」「釜山と福岡」なので。昔あったんですって、海底を繋ぐ花路というのが。(注:釜山(韓国)と九州(佐賀県唐津市)を壱岐・対馬経由で結ぶ全長約200km〜250kmの海底トンネル構想。1980年代より民間団体などが推進し、日韓の物理的な連結による経済・物流向上を目指すプロジェクトだが、約10兆円の巨額建設費や安全保障上の懸念から、実現に向けた課題は極めて大きい)これを「華路計画」とセイルさんが言ってたんですけど、そんな事実ないですね(笑)。
柴山:山下さんご自身としては、水面下で進んでいるものもあるんでしょうけれど、他には。
山下:今はもう、呼ばれたら出る…。情けない話なんですけどコロナで心が折れちゃって。今まで芝居なんて自分から「やめた」と言わない限りはできていたことが、できませんと世の中から言われた。そうなると自分たちの価値って? 必要ないと言われているようで一回ブワッと落ちたんですよ。その中で、『十二人の優しい日本人たち』がオンラインであったんですよ。それ見て泣いて。
柴山:ありましたね、画面を分割してのリーディング。
山下:やっぱり面白い…最初に芝居が面白いと思ったのが『十二人の優しい日本人』なんです。筑紫ホールでやった。坪内陽子たちとみんなで見に行ったんですけどその時に会場がみんな笑ってるんですよ、その声でセリフが聞こえないんですよ、でもやっていることは分かるんですよ、自分も一緒になって笑っているその空間が、今思い出してもドキドキしますけど、こんな素晴らしい空間ないや!というのが芝居を続けているモチベーションになってる。20~30年ほど前ですね。
その後、一回、芝居どうかなと思った時は永井愛さんの『歌わせたい男たち』をまどかぴあで見たんですよ。その時もみんな笑ってるんですよ。あれ、校長先生が歌わせようとしているんですけど、屋上で「お前たち何も考えなくていい、バカだぞ」と言ってる、でも観客はみんな笑っている。でも何人かは笑ってないんですよ。それが目の端に入ってきて、「あ、周りは笑ってるけど言われてること感じて、笑ってない人たちと俺も共感できている」のでただ笑うだけじゃない世界もできるんだ、とまだまだ(芝居には)魅力があるんだと。コロナの時の配信もできなかったということも、やっぱりライブということにこだわりというか憧れがあったんですね。
柴山:なるほど…。最初はひょんなことで芝居の世界に入ってしまったようですが、やっぱり芝居…お好きなんですよね。
山下:そうですね。それとありがたかったのは、大阪とかに何回か1カ月くらいいかせてもらって。最初はわかぎえふさんの「リリパットアーミーⅡ」に河原新一と上瀧たちがオーディションを受けて出たんですよ。その翌年に劇団WaDaChi轍の『ひびきの石』ってお芝居にわかぎさんたちが見にきて、「次にこういう芝居があるから山ちゃんも出ない」と言ってくれて上瀧たちと3人で一カ月住んで『天下御免の馬侍』っていうのに出たんですよ。その後に西鉄ホールの企画で「劇団太陽族」の『往くも還るも』も1カ月間大阪で稽古してやって。それがちょうど阪神淡路大震災の10年でその時丁度神戸で再演が決まって大阪で稽古して。大阪でやってらっしゃる方の空気とか厳しさを身近で感じられたことも大きな要因の一つだし。坪内守とか林田麻里とかが東京でやってる…もちろんやめちゃったのもいるんですけど、そういうのを聞くことができる立場にいることができたというのも運がよかった…本当にこれだけ芝居を続けられているのはやっぱり運がよかったんだと思います。今でも太陽族は付き合いありますし、自分の芝居の中では大きいですね。
柴山:最初の二年はばあくぅに所属されましたけど、その後はご自身で作ったもの以外にどこかに所属はされてないじゃないですか、そういう意味ではよその水を知る機会もあまりなく、だからリリパにしても太陽族にしても、他所の劇団を知る機会があったことは大きいですね。
山下:大きい。自分のためになってますね。
柴山:そうだったんですね。いろんな活動をされて興味深いお話でした。ありがとうございました。

