柴山:劇団費みたいなものは取ってたんですか?
集地:最初から取ってますよ。最初安かったね。で、劇場を持ってから多分5000円になった。
柴山:家賃どのくらい覚えてます?
集地:家賃はね、安かった。10万もしなかったんじゃ。8万とかそんな感じ。
柴山:しかも中を好き勝手にしていいんですよね。結局、再開発で潰されることになって手放したんですよね。
集地:そうですそうです。
藤岡:私は舞鶴SHOW会に来たら一生芝居できるよって言われて。
柴山 なんかすごい誘い文句。舞鶴SHOW会は照明なども専属でいたんですか?
集地:あの照明は知り合った人はずっと続いたのね。だから金子君なんか最初手伝いに来た時から最後まで照明でいたんだよね。

三留:うん、そうですよ。
柴山:劇団員だったんですか。
集地:劇団員。だけど、照明しかしない。
彰田:僕が入ってすごいなと思ったのは、芸工大出身の人間が多いじゃないですか。だからスピーカー設計は本職で小杉さんでしょ。で、金子君は照明いじるしね。だから作ってるんですよ、スピーカーも照明もね、ミキシングもね、そんなの劇団の中に普通はいないでしょう。だから創造的なんですよ、すべてがね。『星に願いを』、あれは見事でしたよね。星座パネル。星座を全部豆球で。星座の位置に…あれ500個ぐらいつけたって言ってましたよね。それを見た九電が(作品を)買ったの。でも小杉さんが「同じものはしない」って言った。「僕らは同じ公演はしないので」って言うので、他の作品をした。ただ同じ作家の『翼』というウルトラマンが生まれる物語をやったんですよ。
柴山:再演をしたくないということですか?
彰田:そうです。
集地:でもしてるよね。しょっちゅうね。
三留:『人間の証明』は2回やってるしね。『今は昔、栄養映画館』も2回やってる。
彰田:だから売るときのプライドみたいなのがあったんじゃないですか。安売りはしない。僕らは常に前を見てるみたいな(笑)。
舞鶴SHOW会とクレイジーでこう、小杉さんがずっと携わってるやってるじゃないですか。今の福岡の大道具作ってる兄弟船の中島君とかは、小杉さんから習ってるようなもんやもんね、大道具とかを。それとか芝居とは違うんだけども、北九州演劇祭って僕ら第8回で出てるでしょう。でも第1回目は僕らが北九州に行ってたんですよ。福岡の人間が。どういうことかっていうと、劇作家協会っていうのができて、第1回北九州演劇祭に日本の劇作家が来ることになったわけですよ。劇作家大会が開かれて、井上ひさしさんとかそういうのが来るっていうのを僕らは知って。これはすごいことだって言って、北九州の行政とか何も動かないから福岡の劇団に呼びかけて、そして北九州演劇祭の第1回を盛り上げようって言って僕らが行ってたんですよ。演劇の地位を高めようという話し合いとか。第1回目は北九州まで出向いて劇作家大会っていうのを、鴻上尚史も来ましたもんね。で、その時に『上海バンスキング』を書いた…斎藤燐さんがシアターポケットに来たんですよ。あの話し合いに。
柴山:何の話し合い?
彰田:劇作家協会の劇作家大会を北九州でやるけれども、実は福岡からみんな行ってるんですよって。だから福岡から北九州に出向くよりも、福岡で大会の企画・運営について話し合いませんか、ついては僕らの劇団のそのシアポケがあるからって言って、斎藤燐さんが来たんですよ。その時に『上海バースキング』は最初持ち劇場でやったんですかって言ったら、いや、ここの持ち劇場より狭いところでやったって言って。「まだここはタッパがあるからいいよ」って。
小杉さんのすごいところは、劇団以外でもそういう小劇場を作るときに呼ばれる。
三留:ちょっと話を聞いただけですが、夢天神とかも企画段階で意見を聞かれるようなことがあったらしい。そこで、当時のいろんなことに使える何でも空間コンセプトでは、かえって何をやるにも使いにくいということ、劇場として使うための最低の条件、可動式客席の原案なども話をしたらしい。杮落しにも参加させていただいたように、設立までのあいだ、小杉の考える理想の小劇場に近づけるよう話をしていたようです。
彰田:だいたい普通は(貸し館だと)芝居のことを考えてない劇場作りをするから。(小杉さんは)プロの音響家でもあるからね。
柴山:小杉さんってRTU、あれもされてましたよね。で、その時に博多座建設のための、こんな風にしたらいいですよといった要望書を、やられたの小杉さんでしたよね。
彰田:そうなんですよ。だから湾岸扇貝(湾岸劇場博多扇貝)…の人間もえっと、シアポケをいつも借りてましたもんね。だから彼ら(クロックアップ・サイリックス)も意外と小杉さんを慕ってたというかね。
柴山:劇団員はだいたいどのくらいの人数だったんですか?
集地:いや多いときは20人ぐらい。出たり入ったりが結構。全部裏方入れて。劇団員として会費を払ってる人。
藤岡:舞鶴SHOW会の時? そんなにいたっけ。
集地:いたよ。だって募集もかけてたじゃん。で、知らない人いっぱい入ってたじゃん。
三留:一人一人覚えてないっていう。
集地:だって打ち上げの時に大人数30人ぐらいいたじゃん。
藤岡:打ち上げの時は、だってお客さんも一緒にいるから…。
集地 居るけど劇団員も20人近くいるから、そういう。
彰田:その時は(団費は)5000円とかじゃなかったんでしょう。安かったんでしょ?
藤岡:いやいや、シアターポケットができてから5000円。劇場持ってなかったときは3000円とか。
柴山:公演は既成戯曲が多いですが、これ上演許可は…
藤岡:(笑)。内緒です。
三留:途中で何回か取ってるのね。
藤岡:『靴のかかとの月』をやった時に、なんかクレームが来たんですよ。「上演許可取ってないんじゃないか」て。作者の鈴江俊郎さんから。それでそれから取るようになったんですけど。それでなかなか戯曲探すのに困難になって。私がなんか頭にきてやめるというところに繋がって、なんか上演許可が取れなかったんだと思うんですよ、あれも。
彰田:だけど、別役さんとかはね。上演を許可するっていう自筆のハガキが来るんですよね。
藤岡:でも取れないのが一個あった。これはどことかの劇団に書き下ろしているのでって。別役さんのでも。
彰田:僕が申し訳なかったなと思ったのは、『砂の楽園』の時。俺が東京に行った時、面白いって(許可を)取ったわけよね。(上演料が)7万円って言われて払ってしたよね。だけど、あの脚本にもなってなかった。向こう側で行った時にコピーの台本があったけん、買ってきたったい。それを見せてこれしたいですねっていう話で。
藤岡:でも上演料が7万。
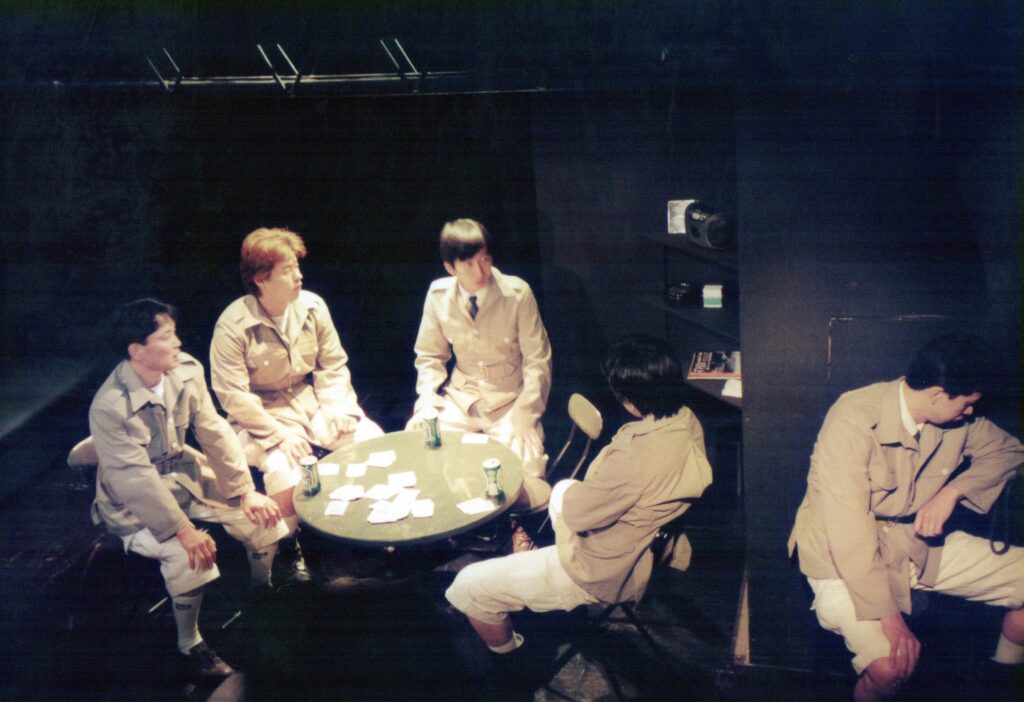
中山ヨシロヲ・石井まこと(敬称略)
柴山:では経済的にはどんな感じだったんでしょう?
藤岡:家賃は払えてました。あとよそに貸してたので、それも合わせて家賃だけは払えてたかな。
柴山:お芝居のチケットノルマがあったわけではない?
三留 ない。
柴山:客席はいつも満席だった感じなんですか。
三留:いやいや。
藤岡:2人の時あったね。あれ、台風だった。
柴山:劇団員が客演することについては、問題なかったんですか?
藤岡:禁止ではなかったけど、あまりいい顔はされなかった。
集地:でも、舞鶴の時はあんまり客演に行ってないでしょ。
藤岡:だって二か月に1回(公演が)あるんだもん(笑)。終わったら次の予告編やってたよね。あれ、予告編やってたのはクレイジーになってからかな。
彰田:そう。その稽古が大変よね。まだできてないのにっていうね。
藤岡:お芝居するのに、逃げ道がないとダメだって言ってたから。この芝居だけに集中してたらダメだと。役者は逃げ道がないとダメだって言って、予告編作ったり、公演が終わった後、一芸大会をやるから一芸考えとけって言ったり。まあみんな遊んでました。
柴山:予告編は別に逃げ道というより、むしろ首を絞めるような…(笑)。劇団員の皆さん、仲良くやられていたんですね。レクレーションなどもやってるし。
藤岡:集地さんが仲良くさせてた。レクリエーションクラブくらいになってた。だから集地さんが(劇団員では)なくなったからレクレーションなくなったんですね。
集地:冬は長野まで車でスキーに行って。
藤岡:舞鶴SHOW会の時ね。
柴山:2ヶ月にいっぺん芝居やって、車で長野に行ってスキーもやって、めちゃくちゃすごいじゃないですか。
彰田:だからそれだけ若かったということですね。
三留:家族ほったらかしですよね。
集地:宗教みたいな感じですよね。
彰田:下手したら仕事の合間をみて芝居してましたよね。
藤岡:公演終わって、もうそこで宴会するんです。上にちゃんと台所があって、料理が作れる。
柴山:シアボケの上に?
三留:アパートぶち抜いてるから。そこで上の1部屋丸々昔のまんまって。
集地:変な作りでキャバレーの作りと、住んでる人が棟の中に一緒に混在してるんですよ。半分は住居なんで、住居の人が出て行くと、そこをまた借りて広げるとか。
彰田:クーラーはあるんですよ、エアコンは。つけたいならみんな100円払えみたいな。
集地:クレイジーになってからでしょ。
彰田:あ、クレイジーになってからか。やっぱり、電気代もかかると思ったんじゃないですか、小杉さんはね。
柴山:そうか、電気代とかもいるわけですよね。だから家賃だけじゃないわけだ。
藤岡:宴会やって、みんな飲んでくれてるんで、朝まで飲むんですよ、そこで。で、夜潰れたら寝て、で、起きたらまた飲んでみたいな。誰かが起きてて、なんかそれ延々と続くんですよ。次の日、そこから仕事に行って、帰ってきたらまたやってるみたいな。
三留:そういうことがありましたね。
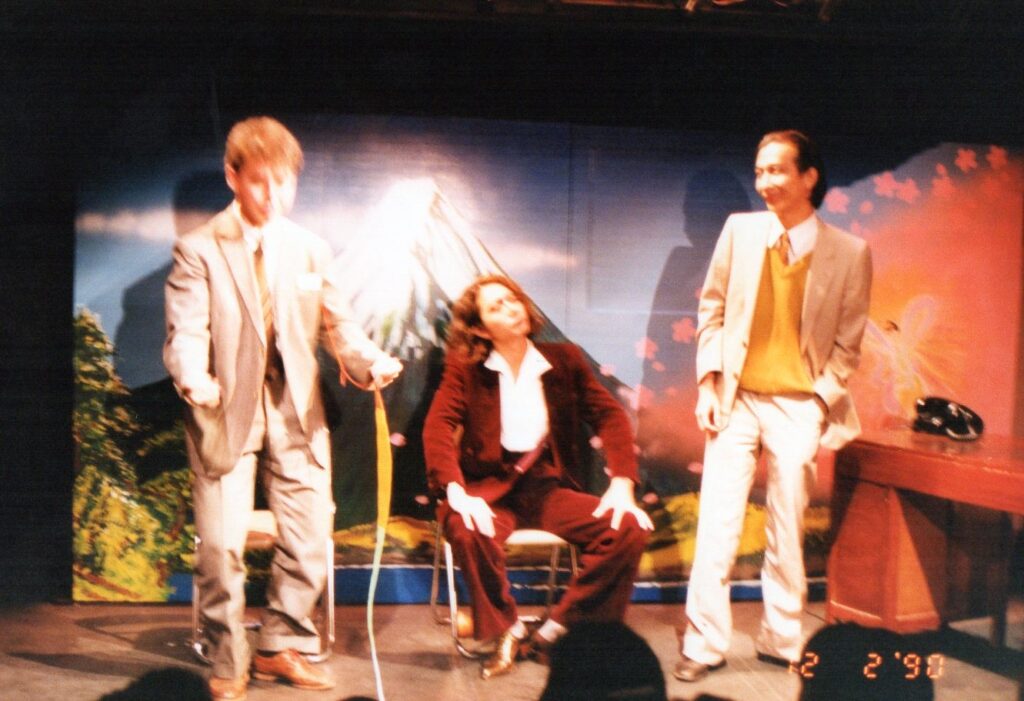

彰田:三留君がね、本番の時にね「今日やばい」とか言うわけよ。「ポケベルが鳴るかもしれん」とか言ってさ、結構本番寸前に鳴った。「今日呼び出しがあるかもしれん」とか言って本番前になんかあったよね、システムエンジニアやけんさ。
三留:本番前一時間ぐらいの時にさっと会社まで行って、片付けて戻ったこともあった。もうメイクかかってんだけど、そのまま会社に行って。
彰田:そんなことしながら芝居する劇団ってないでしょうね。小杉さんが、芝居じゃ食えないって断言してて。それが僕は嫌いだったんですけどね。「いや、なんとか食いましょうよ」って言うんだけども「彰田君、芝居じゃ食えない」ってね。だから生活をきちんとしながら芝居をしないとって言ってた。そういう考えがあったから、途中、自分が食えなくなった時に芝居ができなくなった感はあるかもしれないね。やっぱ生活をきちんとしないと芝居ができないってね。だから「芝居しましょう」って言っても、あの「もうちょっと待っといて」って言って、そのまま亡くなったっていう。
柴山:プライベートも大切にしたいからって言って辞めていく人っていうのも結構いらっしゃったりしたんじゃないですか。
藤岡:仕事がなくなったとかありましたね。バイトでつないでた子とかは食べていけなくなったりとかすると、いつの間にかいなくなったんですね。
柴山:先ほど去る者追わずっておっしゃいましたけど、小杉さん、もう仕方ないねっていう感じだったんだ。
彰田:そうそう。だからその人の生活までは面倒見きれないと。
柴山:2ヶ月に一度公演をやってたら次から次に芝居が来るから、お稽古中などにいなくなることもあった…?
藤岡:それはない。
彰田:そういうの無いね。見て入って、頑張りますって言ってそれを最後に結婚したやつはおるけどね。
柴山:舞鶴SHOW会からクレイジーボーイズを作るっていうことになった理由はご存知ですか?
藤岡:ちょっとね、ゴタゴタがあったから。
彰田:僕は芝居がものすごくしたかったわけですよね。小杉さんになんでクレイジーボーイズにしたんですかって聞いたら、本当に自分も芝居がしたいと。ただ青春真っ只中の人間がいっぱい揃ってるから、男女関係とかいろいろあるじゃないですか。そういうのでごたごたしたくないと。芝居のことだけ考えたいと言ったのを覚えてます。
柴山:では舞鶴SHOW会からクレイジーになった時っていうのは、劇団員も総入れ替え?
彰田:いや、違いますよ。その面々を生かして、新しい人間も入ってきたっていう感じですよね。ただ、リスタートっていう意味での新しい劇団だから、芝居のことだけ考えるような人間を揃えたいみたいなことを言ってた気がしますよね。
舞鶴SHOW会をやめるっていう感覚ではなかったような気がします。名前を変えるという感覚やったような気がするよね。そうじゃない?
藤岡:やっぱりよくある劇団中の恋愛関係でちょっとごたごた。
三留:それどうするんだっていうのが一番の理由だったと思います。
柴山:劇団として方針を変えるとか、作品の何かを変えるとか、そういうことも全くなく。
三留:まあ全くそうじゃなかった。
柴山:名前は変わったけど、気持ちはリセットしたけど、はたから見たらそんなに変わってない?
三留:それでいいと思います。
柴山:小杉さんがオリジナルを書き始めたっていうのはいつ頃ですかね。
三留:割合は早めに書いてるよね。
藤岡:『星に願いを』はオリジナルだったです。舞鶴SHOW会の第3回はオリジナルです。
柴山:小杉さんって書きたい人でもあったんですか?
三留:書きたい人…になったのは後の方だと思うよ。やりたいっていうのが強いと思う。かき集めで寄せ集めたんで、メンバーがめちゃめちゃなんで、これに合う既製の脚本なんかないよっていうのが一番大きかったんだと。
柴山:では書くときは割と当て書きみたいな感じだったんですか。
三留:そうそう、当て書き多かったですね。
藤岡:世の中には優れた脚本がたくさんあるから、それをやった方が役者として成長するんだっていつも言ってた。なので、既成戯曲の方が多いと思います。
彰田:持ってくる芝居がまた妙なんですよね。変わってるっていうか、よく見つけたなって。名古屋の『ハモニカ』(伊沢勉)。今じゃあ意外と名が知られてるけども。
藤岡:そうですね。『ラ・ン・ド・セ・ル』(伊沢勉)とかも。

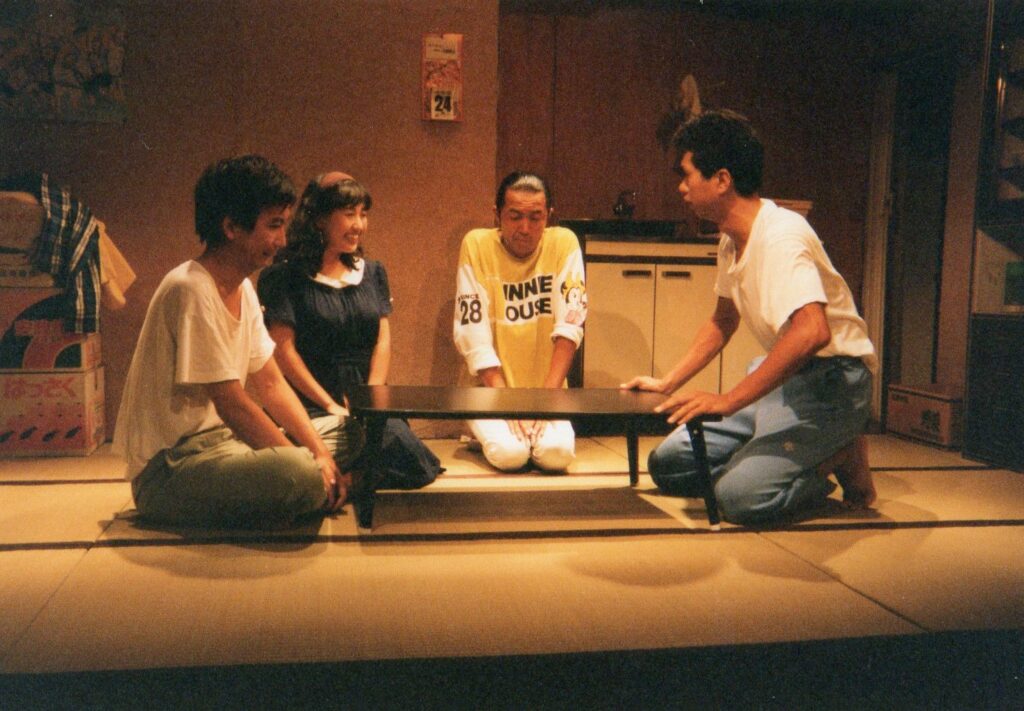
彰田:『人間の証明』は佃(典彦)さんだっけ、あれも絶対知られてないもん。こんなの。
藤岡:『人間の証明』、面白かったね。今見ても思います。
彰田:話はまたちょっと変わりますけど、最後、『ハムネット』ではなく『金メダルへのターン』ですね。2002年の6月が初演で、9月に追加公演で再演した。オリジナルですね。
柴山:芝居を作ってる上での意見とかも自由に言える空気でしたか? それとも小杉さんが言うのが絶対?
藤岡:自由に言ってましたよね。
彰田:みんな好き勝手やってます。
彰田:だけど、小杉さん自身が好き勝手にやってるけども、合わないところはきちっとやっぱ言いますよね。
三留:それはやめてとか言う。
彰田:あの別役の時で面白かった演出が、僕とたけさんがやってる時にさ、こう2人でやりとりしてるわけですよ。僕が「なんですか」とか言うセリフ、で、お菓子かなんかを出すシーンがあってね。で、脚本にはただ「お菓子を出して」だから、こう出すわけですよ。それを小杉さんが「それ犬みたいにやって」って言う。そしたら、たけさんが「う」って(言う)。で、俺が怒るっていう(笑)。犬みたいにやってっていうのがね、2人とも分からんじゃないですか。なんかなって。たけさんがお菓子を出して、俺の顔見て「う」って言う…あれやってて面白かったけど、犬みたいにやってっていう演出って、意外とないよね。だから「こうして」じゃないんですよ。小杉さん自身も、どういう風に僕らを動かしたいかっていうのを、見たかったんじゃないんですかね、ある意味ね。
柴山:例えば現代劇場からクレイジーボーイズに入ってきた人がいるわけですが、芝居のタイプが全く違うとは感じなかった?
三留:そういう風には感じてない。それぞれ違うから、ああ、そういうタイプなのとは思うけど、現代劇場とうちとの違いみたいな、そういう見方をしなかった。
彰田:パーソナリティを大切にしてるから、別に違うとは思わないわけですよね。
三留:この人とどう合わせるかっていう話でしかないから。
彰田 だからテアトルハカタの人が最初にあのNTTの『以心電信』を演出した時にびっくりしちゃったもんね。その人が「どうすればいいですか小杉さん」って聞くわけよ。俺たちは知っとうけん、「いや、どうしてとかじゃない、自分がどうしたらいいかっていうのを小杉さん求めてるよ」って裏で話したりしてね。(テアトルハカタの)野尻利彦さんはやっぱね、事細かく演出するから。
藤岡:そうなんだ。私、他所を知らないよ。逆にね。
柴山:皆さん、ほかの劇団の作品はご覧になってたんですか?
藤岡:私は結構見てました。チラシを持っていた劇団は必ず見ることにしていたから。アマチュアのは結構見てました。
集地:いや、僕はあんまり。あんまり興味がない。
彰田:僕は見てましたよ。
三留:やるのは好きだけど、見るのはそれほどでもないんじゃないかな。今も見てないもん、全然。
*と、ここで会場にしていた赤レンガ文化館の利用時間が過ぎてしまいました。そんなわけで皆さんの写真も撮れず…。後日、皆さんに最後の質問を送りました。みなさんの回答で、見えてくるものもあると思います。
「ふり返って、舞鶴SHOW会、クレイジーボーイズは福岡の演劇シーンにおいてどんな存在だったと思いますか? またご自身にとってどんな存在だったのか、こすぎさん亡き後、思う所があれば教えてください。」
藤岡恵美子さん:アマチュア劇団でありながら自分たちの小屋を持っているうらやましい劇団と見られていたと思います。
舞鶴SHOW会、クレイジーボーイズは私の芝居の拠点。小杉さんがいなくなって、私の芝居する場所は永遠になくなってしまったというか、永遠にそこにあるというか、とても大切な場所。

自分たちの手作りの小屋を持っているということは自慢でした。「自分たちの稽古場を持つんだ」と言われて、地図を頼りにたどり着いた場所。「竜宮城」。ピンクサロンと言われる物を見るもの初めてだったけど、小杉さん、集地さんたちが壁や床をガスガスと壊して、とにかく、二階の部屋が見事になくなって、梁だけになった、こんなショーゲキ的な現場に居合わせたのは、あの時の劇団員以外誰もいない。私は、壊された物を外に運んだり、壁紙を貼ったり、掃除したりというお手伝いしか出来なかったけど、その後、劇場に顔を出すと、床がきれいになってたり、ハシゴやキャットウォークができてたり、照明ブースができてたり、すごいなーすごいなーと、ただただ、ワクワクと、その場にいました。
芝居作りもその延長にあって、人生経験の少ない私にとって、ビックリすることの連続で、とにかく、すべてが楽しかった。
シアポケは小杉さんの夢だったのかな。私たちはまた小杉さんと一緒に芝居することを望んでいたけど、小杉さんの芝居(劇団クレイジーボーイズの芝居)は、シアポケとともにあって、シアポケが解体されたときに、一つ、小杉芝居(劇団クレイジーボーイズ)の幕が下りたのかなと、今になって思います。
三留豊さん:福岡の演劇シーンでというのは、個人的にはまったく考えたことないです。思えば、ちょっと特異な存在であったとは思います。公演のペースだったり、料金だったり、自分たちで劇場持ってたりということで・・・。それが何の意味を持っていたかというのは知ったことではないと思っています。こちらは好きなようにやっていただけなので・・・。
私は自分が「福岡の演劇人」だと思ったことはないです。「演劇人」ではないと思っていました。趣味というか道楽(何の意味もないのに金や身体を削ってまでやるという意味で)をしているサラリーマンというだけです。
小杉さんのお芝居だけに興味あるというより、自分のやっていることだけ興味があって、もともと他の人のお芝居は知り合いが出るとかの理由があってみるだけで、「これ見に行きたい」ということはありませんでした。

自分の娘が高校生くらいで、娘の方が音楽活動などで年間ステージ数で負けてしまって、そろそろ三留さんちは世代交代だなと思ったので、あとは娘が好きにやればいいと思い、自分はもういいかな、好き勝手やれるだけやってきたし、ということで、以降は積極的に自分から動かなくなりました。
小杉さんのことについては、自分がどう思っているか、自分でもわかっていなかったと思います。死んでしまったときに、「自分でわかってなかった。小杉さんのこと大好きだったんだ。」と思いました。嫁にそう言ったら、「知ってたよ」と言われました。小杉さんがいたから、けっこうきついときもあったからやってこれてたんだと思います。感謝と淋しさが残っています。
彰田新平さん:こすぎきょうへいは芝居が大好きだった。
こすぎきょうへいはシアターポケットが大好きだった。
僕も芝居が大好きだった。
僕もシアターポケットが大好きだった。
そこに仲間が集まり、ごく自然にこすぎきょうへいの目を通していろんなものを見ていた。
僕らは、こすぎきょうへいが世界を見る姿勢みたいなものをけっこう気に入っていた。
村上春樹の「海辺のカフカ」のラストを引用するなら…僕らはみんな、いろんな大事なものを失い続ける…らしい…その大事なものを頭の中にとどめて、僕らは自分の心の正確な在り方を知る為に、たまに整理する事が必要…らしい…そしてそれらは、永遠に僕ら自身の頭の中で生きていくことになる…らしい。

僕のこれまでの人生において、その時のその場所のその仲間達は、頭のポケットに入っている大事な宝物のひとつだ。
2025年こすぎきょうへいの10周忌において、元劇団員だけでなく福岡の演劇人がいまだに偲んで集う仲間たちにとっても、こすぎきょうへいとシアターポケットが大好きだったに違いない。


