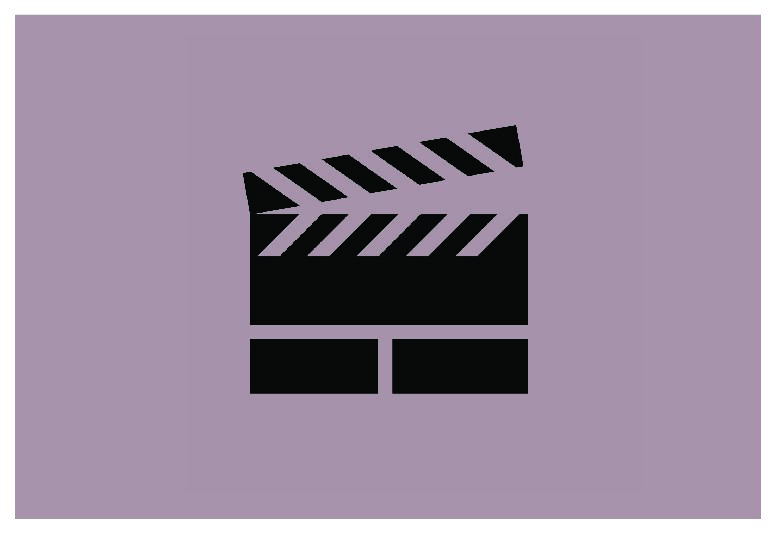本の紹介(9)
『2.5次元文化論 舞台・キャラクター・ファンダム』須川亜紀子 青弓社 2021年
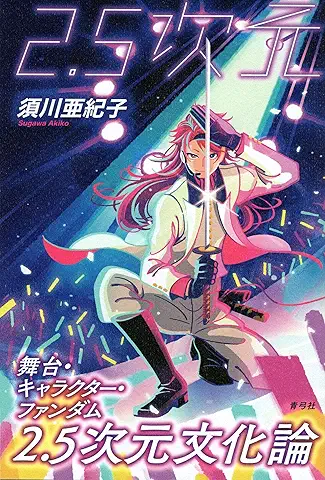
いつの頃からか「2.5次元芝居(舞台)」の数が急増して、私の周りにもファンがいる。それで、いつだか私も勉強のために見に行こうと、『テニスの王子様』ミュージカルを見にいった。俗にいう『テニミュ』である。その時に感じたことのいくつもの点が、本書のおかげで合点がいった。
本書は、横浜国立大学大学院教授による2.5次元文化についての論考である。真面目な研究をまとめたものだが内容が身近ということもありとても読みやすくて面白い。今ではよく耳にする「2.5次元」という言葉は、実は1970年代頃からアニメファンの間では「声優」を意味するジャーゴンだったらしい。それが3回の声優ブームの後(その間に「声優=中の人」と呼ばれるようになった)、『テニスの王子様』ミュージカルがきっかけで現在多く使われる「2.5次元」という言葉の定義――アニメや漫画を原作とした(特にキャラの再現性が高い)舞台作品、固く言えば「役者の虚構性が高い身体を通じて表現されるキャラクターの再現性を重視した演劇及びそのキャスト」――に落ち着くようになったという。『テニミュ』は、演劇業界においても、2.5次元ミュージカルにとってもすべてのターニングポイントである作品らしい。
興味がある方はぜひ読んでほしいので、私がなるほどと納得した点だけをいくつか紹介しよう。まず私が『テニミュ』を見にいった時に感じたのは(失礼ながら)役者の演技の未熟さだった。それまでも漫画原作の舞台はミュージカルだけでなくストレートプレイであれ歌舞伎であれ能であれ見てきているが、そんなことは感じなかった。だが、2.5次元舞台では少年・少女の成長譚のナラティブが多いことから、新人を起用して、役者の成長、役者と物語内のキャラクターの成長を重ね合わせて見る(見守る)…という楽しみ方があるという指摘に、「そういうことだったのか!」と膝を打った。『テニミュ』の説明(分析)において面白いと思ったのは、卒業システムを導入していること。「○代目キャラ名」という形で、役者が(まるで登竜門のように)テニミュを卒業して羽ばたいていく(?)のである。そして未完成な新人俳優を新たにキャスティングする…。これもまた、作品内容が成長譚である事を思うと、重ね合わせた「成長」システム、まるで学校のようなものなのである。
また私にとっては、ミュージカルナンバー(歌詞)がやたら説明的であることも残念に思った理由の一つだったが、それも気のせいではなかったらしい。ブロードウェイのミュージカルを基準とすればきわめて「非ミュージカル的」に状況説明を歌っているとのこと。しかもミュージカル的文法(突然歌いだすというような)に対して自己言及性が強いことも特徴の一つに挙げられるらしい。
もちろん私の(観劇時の)不満の理由が明らかになっただけではなく、本書は新しい発見、知識もたくさん得られる。2.5次元文化には詳しくなくとも、見知ったものに繋がりとても面白く読んだ。例えば日本のメディアミックスについても、思い起こせば平知盛の最期などは、平家物語は当然のこととして、能『碇潜』になり文楽や歌舞伎でも『義経千本桜』の中の段で見せ場になり…となるわけで、大昔からこういう形で消費および生産してきた…つまり(現代の)ファンによる二次創作も同線上にあると考えてもいいわけだ(それを大塚英志が生産者でもあり消費者でもある「プロシューマ―」という造語で説明している)。「ボイスアイデンティティ」という概念が登場したというくだりも面白く、翻ってAI使用無法地帯の現在、勝手に俳優や声優の声を使うことへの懸念、反対表明のニュースに繋がった。
日本独自のものとして世界でも認められつつある、2.5次元舞台。文化的にもそして経済的にも1つのジャンルとして成立している。が、今後も定着するのか、はたまた変容していくのか、それを考えるためにもまずは読みたい一冊である。