本の紹介(7)
『spring』恩田陸 2024年 筑摩書房
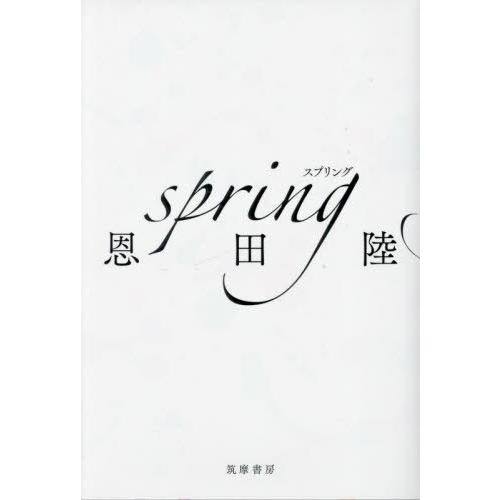
『spring スプリング』 恩田陸
幸せな本である。
なぜなら、バレエに愛されバレエを愛し、才能ある人たちと共にバレエを楽しむ人たちの小説だから。つらい努力や、自分への落胆や、誰かへの嫉妬や、怪我やアクシデントによる絶望や、その他ありとあらゆる負の要素がない。ただひたすらに、バレエをやることが楽しくて、互いに刺激し合って高め合って、そんな人たちの創造の物語である。
その意味では、同じ作者の舞台もの『チョコレートコスモス』の方が小説として面白いかもしれないし、『蜜蜂と遠雷』の方がドラマティックで引き込まれるかもしれない。特に後者は、ページを繰るのがもどかしく、でもその世界をゆっくり味わいたい、なんて矛盾した気持ちで読んだものだ。その二作がオーディションやコンクールなど「他人と競う」ことを通して演劇の面白さやピアノの奥深さを描いたのに対して、本作はそれが一切なく、スポ根的な達成感もカタルシスもない…のにバレエを見たいと思わせるのだから、さすが恩田陸である。付け加えておくと、ここでいうバレエとはクラシックバレエではなくほぼコンテンポラリーダンスのことである。
あらすじをざっくりと言えば、天才的なバレエダンサー(舞踊家)でありコレオグラファー(振付家)である「萬春(よろずはる)」という魅力的な男性について、3人が語り(それぞれが1章)、最後の章は春自身が自らを語るという構成である。春について語られる中で、彼の踊り、彼が作った作品、彼がいるバレエの世界が見えてくる。
私にとっての本書の魅力は大きく3点。1点目は、ダンスをプロの物書きが言語化してくれている点。例えば、クラシックバレエとコンテンポラリーバレエの違いについて。ある者は「観客に重力を感じさせないバレエがクラシックで、ダンサーが重力を感じて踊っているのがコンテンポラリーかな」と言う。また主人公・春は「バレエは花束なんですよ」と言い、かつてはきれいな花をブーケにした花束(クラシック)だけが商品だったけれど、きれいなものの定義は変わり、花屋が扱う商品もどんどん増え、花屋が扱う範囲が広がった」という表現の仕方をする。どちらもなるほど!と納得する。コンテンポラリーダンスの定義について私自身も何度も考えたことがあったから、この2つの解説にはうなってしまった。
また春の作った作品についても、どのような動きをするのか、丁寧に描写する。身体の動きを過不足なく説明し、同時に作品全体を想像させる。クラシックバレエの評はテクニック偏重になるし、コンテンポラリーダンスの評は作品のコンセプトと表現力重視になることが多いと思うのだが、それらとは違って細やかな「動き」の描写がとても新鮮だった。
魅力の2点目は、コレオグラファーとしての春が作った作品を紹介する…つまり作家の恩田が本作においていくつものオリジナルバレエ作品を生み出している点だ。この本1冊でいくつのバレエ作品を見せてもらったことか! 登場する作品を現実のものとして舞台に上げることができそうだし(いずれ『SPRING』という公演で、本作に登場する『ヤヌス』『KA・NON』といった作品をやるなんてことが実現しそうな気がする)、これだけ紙面では具体的に作品ができあがっているのだから映画化だって待ったなし…なんてテクニックの難易度も知らずに望んでしまう。そして、想像の中で新しいバレエ作品を作ること、恩田陸はとっても楽しかったんじゃないかなと思ってしまう。勝手にシンパシー。
3点目の魅力。それは、バレエの奥深さを描くために――いや、一流の世界は常に、それ以外の「教養」が重要であるということを示している点だ。言葉は悪いが「バレエバカ」ではないということ。スポ根にありがちな、それだけに専念しそれ以外を排除するような狭い世界観を良しとするのではなく、創造には(こと芸術だからかもしれないが)音楽、美術、歌舞伎、映画、小説…といったものが必要不可欠であるということをしっかりと描いている。大いに賛同するし、それがきちんと描かれていることに好感を持った。
感情が起伏する「面白さ」を求める人には、物足りないかもしれない。でもバレエの「豊かさ」を味わうことができるだろう。本書はやっぱり、幸せな本なのだ。


