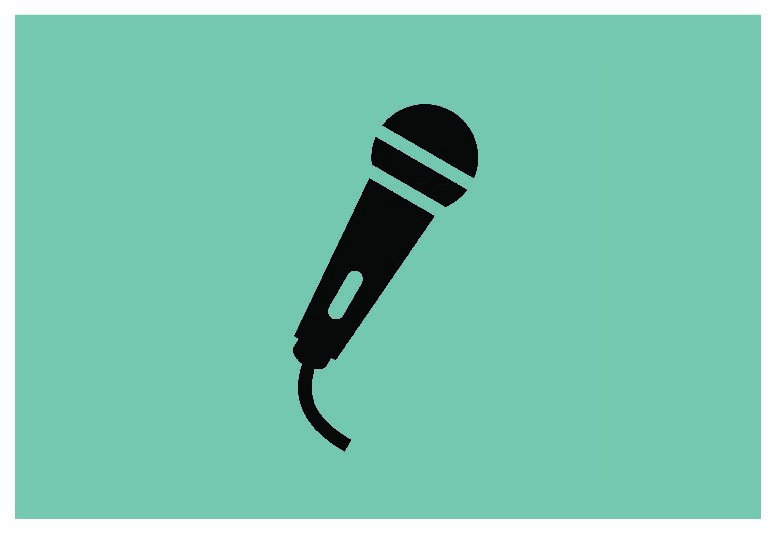本の紹介(6)
『人間一生勉強や …下谷浅草龍泉寺』 本城明信 1998年
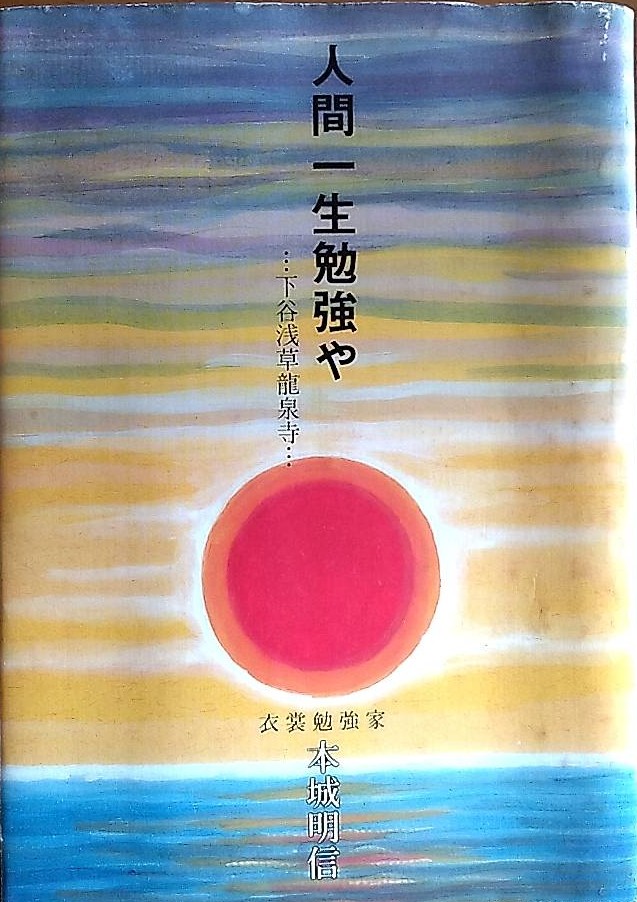
松竹衣裳株式会社に長く務めた本城名信さんの自伝である。非売品、つまりは自費出版であろうからどこでも手に入る本ではないことを先にお断りしておこう。
本城氏は1935年に東京は下谷で生まれた江戸っ子。演劇青年だった時代があるものの、最初から衣裳を生業にしようとしていたわけではない。失礼ながらフラフラといつの間にか松竹衣裳株式会社に入ることになった、というのが正しい表現だろう。テレビ、映画、舞台で俳優たちの衣裳担当で奔走し、会社の都合で東京、大阪、博多で働いてきた。一時代前の芸能界隈の裏を衣裳係の視点から垣間見ることができる一冊である。
とはいえ、正直に言えばとても読みにくい。余計な慣用句が多いわりに説明は足りない。書き手の思いつくままに話は飛ぶし、首をかしげる話の挿入もある。また「劇団」という呼称で書かれているのは彼の博多時代で関わりがあった「劇団テアトルハカタ」のことだけを指すようで(しかし劇団テアトルハカタ自体は後半30ページぐらいにならないと登場しない)、となると博多時代の知人にしか配布していないのかと推測する(ちなみに北九州市小倉の印刷所で作っている)。もちろんすべて目を通したけれど、部分的に面白いと思う所をつまみ食い的に読むのが適している本かもしれないと思う。
福岡に住む私が興味を持って読んだのは、やはり本城氏が福岡にやって来てからの件。1985年、彼は50歳の時に松竹衣裳株式会社が九州出張所開設するにあたって博多に単身やって来た。肩書は「所長」だが(後に事務員を雇うまで)一人きりの出張所で何をやるのか分からないところから試行錯誤をする。地元テレビ局との作品作り、ショーパブ「あんみつ姫」や大衆演劇の「小林劇団」への衣裳提供、また「劇団テアトルハカタ」や北九州の「青年座」との関わりなど、なじみのある固有名詞にフムフムと読んだ。ただ、劇団テアトルハカタや青年座に、どういう衣裳を提供したのか、どんな工夫があったのかなどは一切書かれていない。いや、衣装を提供した事すら書かれていない(巻末にある「衣裳担当をした作品一覧」の中に両劇団の名前と作品名があるのでそこで初めて本城氏が衣裳担当したのだと分かった次第)。特に劇団テアトルハカタについては団員と交わした会話や主宰の野尻敏彦についても触れているので、もう少し「衣裳屋」としての関わりがどうだったのかが読みたかった。
芸能界隈の衣裳の話…というには物足りないが、自伝だと考えれば仕方がないことか。
こういう本がある…という程度の紹介である。