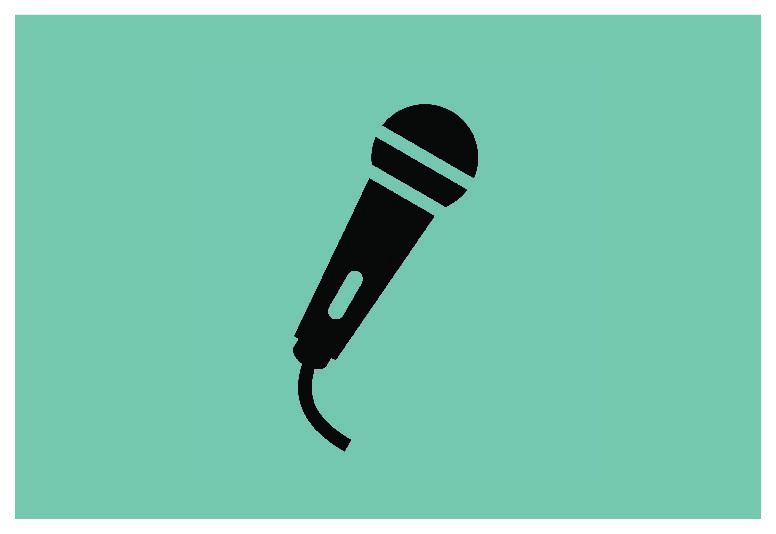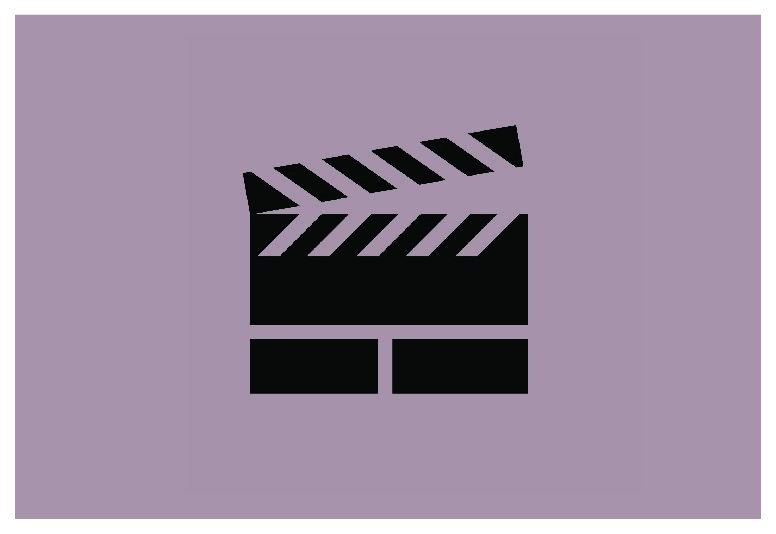「演戯集団ばぁくう」について
「演戯集団 ばぁくう」とは、1988年6月に佐藤順一を代表として結成した、表現者の集団である。HPには、「メンバーひとりひとりが芝居人であるという意識で、あえて、劇団ではなく「演戯集団」(=演じ戯れる集団)」と名付けたと書かれている。
私がばぁくうを知ったのは、大名にアトリエ戯座で公演を見てから。20年近く前の事である。座付き作家のオリジナル戯曲で公演する劇団が多い中、ばぁくうは既成戯曲を扱う稀有な存在であった。新劇の作品をやるという印象が強い。知らない作品をたくさん公演してくれ、ばぁくうのおかげで知った劇作家もいる。2010年からは「読演会」という名で、佐藤による「演じながらの朗読」を定期的に行い、事務所を兼ねていた六本松の「アトリエ戯座」を撤退する2023年4月まで続いた。その数は141回にものぼった。
| 1988年6月 演戯集団ばぁくう結成。 1998年7月 有限会社 演戯集団ばぁくうを福岡市中央区平尾に設立。 1998年12月 稽古場・アトリエ・事務所を大名に移転。 2009年10月 稽古場・アトリエ・事務所を六本松に移転。 2023年4月 稽古場・アトリエ・事務所である六本松を退去。 |
今回は、代表の佐藤順一氏に「演戯集団 ばぁくう」ができる以前のこと、そしてできる経過までを伺った。福岡の演劇の歴史を知る上で貴重なインタビューなので、楽しんで読んでいただきたい。
インタビュー

柴山:どういう経緯でお芝居を始められたんですか。
佐藤:昭和40年にRKBの児童劇団に入ったんです。その当時、KBC、NHK、RKBって児童劇団、放送劇団があって、その一番最後がRKBで、テレビやラジオに出演が可能な人間を育てる劇団。当時KBCもなくなり、NHKもなくなっていたんで。ちょうどKBCが前年39年ぐらいになくなったはずなんです。僕がRKBに入った年はKBCがなくなったから、消えた児童劇団の人たちがオーディションを受けに来てました。
言葉を普通に喋れるようにとか、テレビやラジオに出演するときのルールとか、そういうものを研修しながら実戦で経験させていくという。
柴山:おいくつの時だったんですか。
佐藤:10才。くわしくは覚えてないけど、周りが応募した形だったと思います。僕は全然そんなのやりたいとも思ってなかったし。試験の時にぺら一枚のセリフの掛け合いと歌を一曲と特技を披露するという面接があって。5人ずつぐらいでやる。歌なんて一行も歌えなかったのを覚えています。特技は何もできなかったと思います。セリフの掛け合いだけかなぁ。あんまり覚えてないんだけど。一緒に受けている人たちとセリフの掛け合いをする。10才から15才まで。
柴山:これはお給料をもらえるんですか。
佐藤:そうです。仕事に行けば行った分だけギャラが振り込まれる。翌年からレギュラーが始まったんですよ、テレビの。当時キリンビールの提供で「キリン子ども劇場」というのをやっていたんですよ。RKBの6:56から4,5分の枠かな。よくやるじゃないですか時報前の。『やん坊マー坊の天気予報』前番組かなんか。1週間で1話のドラマをやるという。長いと2週間またいでで1話。月~金で。日本の『夕鶴』とか西洋のだったら『王子と乞食』など子ども向けの。今考えるとものすごく大仕掛けでしたね。スタジオの中にセットも組んでやってましたから。そこでずいぶんやって、それが1~2年やったら、キリンの同じ枠で、今度はお芝居じゃなく『キリンミニサイエンス』という科学番組をやったんです。5年ぐらいやったかな。
柴山:それは子どもが実験するといった形なんですか。
佐藤:キリンのおじさんという人がいて、その人が先生役で生徒の僕ともう一人女の子が、先生から質問されたら答えるような掛け合いする番組でした。九大の教授たちが監修に入ってました。作りとしてはしっかりしてました。確か民放賞とか取ったかな、グランドホテルとかでパーティやったのを覚えています。ちょうど万博の年だったので、万博まで行ってシリーズをやったりね。
柴山:それは楽しい思い出ですね。
佐藤:そう。ロケもいっぱい行ったしね。例えば魚の話だったら、1週間ずっと魚の話をやる。地質学についてとか、九大の教授たちの得意分野を監修してもらって…。
柴山:先ほどKBCやNHKが次々に放送劇団や児童劇団をやめたとおっしゃいましたが、なぜRKBだけが続けていたのだと思われます?
佐藤:さぁなぜでしょうねぇ。やっぱりそういう番組を作っていたからではないですかね。当時KBCとかが作っていたのは『昼のティータイムショー』とかで、演技が必要な人たちが出演する番組は作っていなかった。それは会社の志向性の問題でしょうね。
柴山:『ティータイムショー』というのはいわゆるバラエティ番組のようなものですか。
佐藤:そうです。当時は「タレント」と放送劇団所属の「劇団員」がいたんですよ。タレントさんはピン契約なんです。劇団員は曲の劇団に所属しているから、仕事がないとお金がないんですよ。だけどタレントは所属量がない、契約料が入る。そういう意味でタレントの方が守られている。だからタレントとアナウンサーで番組を回すようなものしか、KBCとかはなかった気がします。NHKは全国ですから、バーターで融通できるから。ただ九州の場合は福岡が元締めだからそこにいる人間が鹿児島行ったり大分行ったりしていた。だから一番最後まであったしその規模を持つ必要があったんです。そういうものもだんだんキー局、東京・大阪・名古屋辺りで作るものを回せばいいということで。VTRで流せるようになったから。当初はまだVTRではなく生本番だったから、その流れで演じる人が必要だった。だから放送劇団を作った。演技部が必要になったから。その需要が放送が始まって10年経ったらなくなって、キー局で作ったものを流せばいい、VTR機能が全国に広がったから。その方が安くつくし、維持しなくてもいいし。それでどんどん地方の放送劇団が解体になったんです。それが40年前後なんですね。RKBは32年開局のはずなので8年ぐらい…後だったんですね、ぼくが入ったのは。42,3年ぐらいまであった気がしますね。
柴山:では佐藤さんが入っていらっしゃったのもわずか数年だったんですね。
佐藤:そうです。5年。中学になると児童劇団を卒業しなきゃいけないんです。劇団があればそちらに進む道もあったけれど劇団は早くに解体になっていたから。KBC劇団だったら今福将雄さんとかRKBだったら下川辰典(のち辰平)とか、劇団が解体した時に東京に行ってるんですよね。斉田明なんかは劇団が解体された後、「劇団道化」を作ったんです。ですから「道化」は当初、放送劇団からの人の寄せ集めだったんです。
柴山:佐藤さんは中学に入る時に児童劇団をおやめになったんですね。
佐藤:ただ僕は番組をやっていたから、所属は生きてたんです。児童劇団は無くなったけれど、演技部で残されていました。二人ぐらいいました。当時、東芝日曜劇場というのが9時の枠であったんですね。2年に1本、九州で作ることがあって、東(義人)さんがRKB演出部にいたので、東京の著名な作家と協力して脚本を書いていたんです。TBSの石井ふく子大先生にお伺いを立てながら作品を練り上げ、収録に臨んでいたように思います。演出担当は四、五人居たように思います。東さんはその中の一人です。ついでながら、在福の放送作家は、香月隆、井田敏、赤星?氏などが強く記憶にあります。前述の「キリン」を持ち回りで書いていました。
柴山:では学校に通いながら、東芝日曜劇場など声が掛かったら出るという感じだったと。
佐藤:そうです。最後が…昭和が終わる年に葬式の話をやったんです(『お葬式人情物語』)。古尾谷雅人とか沢田亜矢子とか(が出てました)。昭和天皇が亡くなったから、オンエアが2年ぐらい延期になって。それをよく覚えていますね。
柴山:お蔵入りはされなかったんですね。
佐藤:僕は観てないんですけどね、1年半ぐらい遅れたかなぁ。
柴山:ではRKBに放送劇団ではなく演技者として所属していたんですね。タレントと同じ扱いということですか。
佐藤:そういうことだと思いますね。その辺りは詳しく覚えていませんけど、呼ばれたら行くって感じで。
柴山:といっても学生だから毎月のお給料をもらうわけではなかったんですよね。
佐藤:そうです。出演ギャラだけ。
柴山:その後は。
佐藤:社長になりたいなぁと思って、商売を。RKBの所属の最後が…NHKの仕事とかもするようになっていたんですよね。ラジオとか、朗読の時間とか昔色々あったんですよ。それをズルズルやってましたね。高校生ぐらいまではやっていたと思います。…で、洋服屋に就職したんですよね。
柴山:この仕事をやろうとは思わなかったんですか。
佐藤:思いませんでしたね。NHKは定期的に番組を作ってましたから、そこで大人たちと会うわけですよ。朝からスタジオ入って夜まで収録すると、途中でいないなと思ったら劇団系の人たちは酒屋で飲んでたとか、すぐケンカするし(笑)。まともな大人じゃないなと思って。かたやタレントと言われる人たちは洒落ていて、蝶ネクタイしてベレー帽かぶって、けっこうなお金をもらっていたんですよね。それで、こっちの人たちの方が洒落てるなと。そんな風に見てましたね。
それで洋服屋に勤めながら、店をやりました。飲み屋です。23でした。最初は居ぬきの店舗を借りて、名義もそのままの店を任された感じで。30ぐらいまで7年間くらい。でも又貸しになるからまともな道を踏んだ借り方じゃないですか、そういうのは感覚的にないから…知人が任せてくれた、その人の家賃の倍の値段で貸すよと、たしか22万くらいだったかな。後で分かった事だったけれどそこの家賃は9万5千円ぐらいでした。でもまぁ、名義も最初の準備も何も要らない、もちろん使い古されたものだったけど。結構楽しくやってました。
柴山:お店はどちらにあったんですか。
佐藤:渡辺通り。高砂です。今のFBSの向かい側あたりです。今やそこはビルばかりになっていますけど、当時は2階建ての、2階が住居で1階が店舗。
柴山:すみません。話をもどして確認したいんですけど、タレントさんは全く演技をしないんですか。
佐藤:いや、演技はするんですけど、放送局の椅子が違うだけなんです。個人契約するだけの技術、知識、経験があるかどうか。劇団というのはエキストラとして使う。タレント契約している人たちは割と東京から流れてきた人たちが多い。当時、ドサシステムというか、東京にいくつか劇団があって、それが地方を回っていたんですね。そこからこぼれた人間たちとか、東京でトラブルを起こして居づらい連中が地方に逃げて行くわけですよ。
柴山:佐藤さんはタレントになろうとは思っていなかったんですね。
佐藤:未練はあったんでしょうね、呼ばれたら行ってましたから。こんな楽な商売はないとは思っていました。でもこんなのはいつまで続くか分からないという意識もありました。
柴山:それでご商売を始めたんですね。飲み屋さんはお洋服屋さんと兼業でなさっていたんですか。
佐藤:半年くらい一緒にやってました。でも最終的には身体がもたなくなっちゃって、7時から店に入って朝5時ぐらいまでやって、ちょっと仮眠してそこから会社に行って…やっぱり上手くいかなくなった。その間も呼ばれたら芝居に行ってましたけど、ほとんどなくなっていましたね。
柴山:30才でおやめになった理由は。
佐藤:夢工房です。その頃の僕のパートナーが石川(蛍)さんと渡(登美子)さん夫妻にインタビューしていたら、役者探しているっていうんで「うちの旦那も役者でしたよ」って伝えたら「一回会ってみよう」と。客演として1年間行ってました。そしたら知っているつもりでいたけど、まったく知らない世界でしたね。それでちょうどもう嫌になっていた頃なんだと思います、飲み屋の金は…後ろめたい気持ちがあったんだと思います。ちゃんとした仕事という金ではないと僕の感覚ではあって。
柴山:客演はギャラを頂けるんですか。
佐藤:夢工房はイベントやってたから。外に出てパントマイムとか。
柴山:では石川さん達が探していらっしゃたのは、舞台に出る役者さんだけでなくマイムや大道芸のようなことをするという…
佐藤:当時、銀之丞(山崎銀之丞)とかいたんですよね、結局、そういうのが一斉にやめちゃったから。僕のきっかけは、演劇の次の舞台のこの役がいないのでやらないかと。そのあと、学校廻りのこういう劇があるよ、童話劇があるよ、とか。僕は自由が利くじゃないですか、だからちょっとやりましょうって1年間やってました。
柴山:お金ももらって。
佐藤:そうそう。じゃ、こっちで本気でやりたいと、夢工房が大きくなれば演劇で生きられる、その道を切り開いてやろうじゃないかと思ってました。石川さん達にしてみたら、育てた銀之丞とか玉川(大学)に行った連中が年に一回ぐらい帰って来てやっていたから「うちは大きくなる」と思っていたのに一斉にやめちゃって。それで若い人間は信用できないとナーバスになって来た時期に僕が来た。で、来てくれて色々やってくれるのはありがたいけれど任せるのは不安だ、またいなくなるかもと。そんな疑心暗鬼な時期と重なっていたような気がします。今考えると。元々から信用されていませんでしたからね。僕は、新しい人生を切り開こうと思って30にしては初心な気持ちだったんですけどね、ここが大きくなれば演劇できちんと生きていけるって。アカデミックな仕事ができるんだ!と。ところがそうじゃなかった。2年目くらいにそういう扱いだと分かってもうやめよう、自分で何とかするしかないと。ただ3年はいないと格好がつかないと思って、3年目が終わるまではいました。それまでにいろいろと要望も出したけど、そんなに不満があるなら自分でやるしかないよと言われて。
柴山:当時は何名ぐらいいらっしゃったんですか。
佐藤:ひとみゆうこ(現・倉科淳子)、中野弘子、ぼくと。劇団員ではないんだけどお友達みたいな若い女性たちが何人かいました。でも何かやる時に、劇団側になって動くのは(先にあげた)二人だけでした。そこに僕が入って、昼間が空いているから掃除をしたり…。
柴山:おやめになって、その時は倉科さんや中野さんはそのまま夢工房にいらっしゃっていたんですか。
佐藤:倉科は、その当時、銀之丞が帰って来てたんですよ。ピクニックの山田さんのお世話でRKBのラジオ番組をやっていたんです。そこに倉科が確か、大谷短大に入る時に、「外部活動は禁じられていますので」という理由で夢工房をやめたんですよ。で、気がついたら短大行きながら銀之丞のRKBのラジオアシスタントかなんかをしていた。(銀之丞を)慕ってたから。それもまた石川さん達にとっては裏切られた、と(いう気がした)。短大卒業してすぐに東京行ったんじゃないかな、安田さんのとこ(劇団山の手事情社)に入った。
だから、倉科…ぼくらは「ひとみゆうこ」って呼んでましたけど、彼女と2本か3本くらい一緒にやったんじゃないかな。
柴山:その頃もすでに夢工房は劇場を持ってました。
佐藤:奈良屋の。あそこができた次の年に僕が入ったんです。
柴山:え、その頃ですか。私は一度だけ芝居を見に行ったことがあります。グリーンのベンチが並ぶ劇場で。あそこでお芝居を見た翌年に夢工房という劇場がなくなったと思います。石川さんに取材もしましたが、ほんとギリギリに行った。
佐藤:その頃は僕はもうばぁくう(演戯集団ばぁくう)を作ったころだと思いますね。僕が夢工房を出たのが1988年の春ごろ。その年の6月1日付でばぁくうを始めてますから。夢工房は92,3年ぐらいまであったんじゃない。雨漏りがしててね、大家さんが修理をしてくれなかったの。唐津の建築会社の持ち物だったの。太っ腹な人であの建物一棟を30万ぐらいの家賃で。でもそれもきつくなって芝居をやるスペースも必要ないと、なくした。なくなってからの方が人が増えた。
柴山:では88年に夢工房をおやめになって、すぐに「ばぁくう」を作った。お一人で作られたのですか。
佐藤:僕と、中野弘子。彼女も石川夫妻と折り合いが悪かったんですよ(笑)。でも芝居がしたいと。だから僕が作るからそれまで我慢し、と。彼女は当時OLさんだったから生活はできていたんで。89年か90年ぐらいまで彼女は「ばぁくう」に入ってもOLしてました。もう一人、名前忘れたけど男と、二橋康浩と4人で。
柴山:ではみなさんが抜けられてしまったために石川さんとしては…
佐藤:そうですね。当然、僕が入って1年間下働きのみたいなことをやった。劇場の建付けしたのも僕と石川さんの二人。真夏の暑い中1カ月かけて。二人物も言わず尻を向けながらトンカンやって作って。反りが合わない状態。中野弘子は当時「牧村霧子」って名前でしたけど、彼女も石川さんの奥さんと折り合いが悪くて。だいたい冷飯食わされている状況というのがあったんで、「もうやめたい」と言っていたのを僕が引き留めていたんですね。僕は3年で辞めるから、ちゃんとプロの劇団で食えるようにするからって。
柴山:その頃の夢工房の作品というのはどんなものだったんですか。
佐藤:石川さんのオリジナルですよ。『冥途行最終バス」とか、『五番街のマリ―』とか。
柴山:作品に対して思うところがあったわけではないんですか。
佐藤:もちろんそれが一番大きい…最初、脚本が悪いと。石川さん、俺もずっとここにいるんだから、石川さんが書くのをやめて名作劇場みたいなのをやりましょうよ、既成の脚本でいきましょうよ、と言った。それが石川さんの怒りに触れた。ここは石川蛍のオリジナルをやる劇団だと。それで渡登美子という奥さんは石川に岸田戯曲賞を取らせるのが夢だと言ってましたから。それで、もうこりゃダメだと。やるたんびにドンドンドンドン脚本が悪くなる。脈絡がなくなるとかくだらないコントを入れるとか。それで僕も失望して。よく酒を飲む人だったから、打ち上げの席の時に――当時の打ち上げは荒かったから――そんな話をする。僕も人生をかけて来ているつもりだったから。それでだんだん険悪になってくる。2年目になると役もつけてくれなくなる。劇場の補修とかしかやることないわけですよ。自分で発声やったり体操やったり、座付きの照明係をやったり。
柴山:当時は他にどんな劇団がありましたか。
佐藤:すぐそばにテアトルハカタがあったでしょ。現代劇場、生活舞台。4劇団で劇団協議会みたいなのがあったから。それが2年に1回、合同演劇をやってましたね。夢工房の劇場を使って九産大の演劇部がキーになっていた覚えがあるんだけど、「炎劇祭」というのを毎年やってたんじゃなかったかな。その頃いたのが、中山君とか。今60半ばぐらいになるんじゃないかな。松尾スズキとかがいたころに九産大にいたんですよ。
柴山:他の劇団に入ろうとは思わなかったんですね。
佐藤:全く思わなかった。テアトルハカタと生活舞台ぐらいですよね知っていたのは。テアトルハカタは近かったから夢工房を借りたりしていて交流も若干あったし、生活舞台も交流はあったけど。僕はどちらかというと夢工房一本だったから、他の劇団なんて見に行くことすらなかった。
柴山:他の劇団を見にいくと文句を言われるということではなかったですか。
佐藤:その空気感はなかったわけじゃないけど、僕が気にしたわけじゃない。ただ僕は夢工房に所属しておきながら他の劇団に様子を行くというのが好きじゃなかった。そういうセクト的なものが僕らの頃って…僕は頭でっかちだったからそういうことがあったんですね。
柴山:今なんかは逆に、よその劇団も見て勉強したほうがいいという感じですけどね。
佐藤:そうそう、だから昔柴山さんがぽんプラザで司会をやったシンポジウムの時に、劇団の垣根を越えて交流しようという話になってましたけど、あの2,3年前からそういうことを言いはじめて、あの時そんな事を石川さんも言っていて。石川さん、俺と、舞鶴show会のこすぎ(きょうへい)さんが出ました。(注:2010年6月19日FPAP主催の「パネルトーク 福岡の歴史をつなぐ~私の好きな劇場~」第二部のこと)
柴山:では、よそではなく自分の劇団を立ち上げて、やっていこうと思われたのは当時としては必然だったんですね。
佐藤:僕はどっぷり入っちゃいないんだけど、見上げた目線で大人たちの演劇に対する思いをいっぱい見ちゃったんですよね。福岡にも僕らの年代って少しいるんですけど感覚が僕だけちょっと遅れてるような気がしますね。演劇の質的にもそうだけれど、演技、演技信条、役作りについても。どうしても僕は一世代前の新劇を追っているところがあって。だから脚本を読むとマッチするんですよ、その時代の感覚に。
柴山:では東京や関西に行こうとは思われなかったんですか。
佐藤:全く思いませんでした。演劇人としてそこまで自信がなかった。ただこの職業をちゃんと作りたいと思っていた。ちゃんと税金払って、一般社会に職業として認知されたいと思った。東京では認知されてるんだから福岡だっていいだろうと。当時僕は福岡にいて、鹿児島にロケに行ったり大分の放送局に仕事に行ったりしていたから、本気になれば販路はあるはずだと思っていた。ばぁくうをやっていた時にパントマイマーとして地方巡業ばかりしてそれで金を作って芝居をやってました。早く自分の稽古場と発表の場を作らなきゃと。この感覚が一世代前の感覚ですね。昔の新劇人たちが、自分たちの稽古場を持たない劇団なんてありえないと言っていた感覚がすごくマッチする。石川さんが反面教師ではあるけれど、自分の発表の場を持ち続けようとした人間ではあるし。そんなのだけが残ってはいるんですよ。
柴山:でも稽古場や発表の場が欲しい(持ちたい)という感覚は、今の人たちにも分からなくはないと思いますよ。あちらこちら回って稽古するより、そこに稽古場があるという部活みたいですけど、その安心感は欲しいでしょうし。
佐藤:それに対して傷は負いたくない…欲しいというけれど負担を負いたくないというのが今の人たちで。欲しいから稼いでこなきゃいけないという感覚、そのためには技術も増して勉強もしなきゃいけない…
柴山:少し話を変えますが「ばぁくう」の名前の由来を教えてください。
佐藤:ひらがなローマ字表記。ローマ字って、母音と子音。BaKuと書くじゃないですか。小さなaとuを入れるのを平仮名にした。
柴山:その理由は?
佐藤:最初漠「漠(バク)」にしようとしたら、「夢工房」を食らうのかって言われて(笑)。先輩から。当時、放送劇団の御大たちが上にいたんですよね。生きていれば80後半から90ぐらいの年齢の。その人たちから新しい劇団の名前を訊かれて、PPM(ピーター・ポール&マリー)の伝説のドラゴンの歌(Puff The Magic Dragon)それが「Puffパフ」って歌なんですが、それにするって言ったら、それは電話を受けた時に捉えにくい、音として破裂音とは行はやめた方がいいと言われたんです。そうかと思って、「ばく」にしようと思った。そしたら夢工房を食らうつもりかと言われた。じゃぁ、表記を「ばぁくぅ」にしますと言った。そんなことより、「演じ戯れる集団」の方に重きを置いた。僕は劇団ではないと、演じ戯れる人たちの集まりだと。劇団のために集まるというのがいやだった。遊び戯れる人たちが、自分の演じることに責任をもって個々に才能を伸ばしていく、そんな人たちが増えればお互いを求めあう人間たちが必然的に集まって、いい芝居ができる。そうすると客が集まる。それが夢の実現じゃないかと思って。だから「演戯集団」の方が大事で冠だから、こっちのほうに何かということで「ばぁくう」にします、となった。
柴山:「ばぁくぅ」は「あ」も「う」も小さいんですか。
佐藤:小さい。僕はそう思っていたんですよ、そしたら中野弘子がOLやってたから経理を全部任せていた。印鑑登録するときに「う」も大きい文字で出していたんですよ。僕はずーっと7,8年も「う」を小さいと思っていたんですよ。そしたら「う」は大きいまま出したと言う。「ばぁくぅ」だと思っていたから「ひらがなのローマ字表記」と言っていたんですけどね。目と音で覚えてもらえるようにと。
たしか90年に会社登録した時に出した書類が逸れになっている。
柴山:88年に4人で始まって、90年にはもう会社の登録をされている?
佐藤:有限会社にしたのが98年の春ですね。
柴山:大名にアパートを借りてやられてましたよね。あれは何年ごろですか。
佐藤:99年だったと思います。だから98年に会社にして、まだ平尾に事務所があったんですけど、99年にあそこに移った。
柴山:では佐藤さんがやりたいと思われていた新劇をなさったんですよね。その頃から私も拝見していますが、99年ごろは他に新劇をされている劇団がなかったので、そういう意味では珍しい劇団として認識していました。他の劇団との交流はなかったんですか。
佐藤:そうですね、僕自身がタレントとしてナレーションとかロケとかしながら自分の所の芝居を作るのに忙しくて、他と交流する暇がないというか。結局、自分たちのアトリエを持つとそこで何かをやりたい。やるために人材育成もしなきゃいけない。場所はあるわけだからできる。その事で一日が過ぎていく。昼間はロケやナレーションに行っていたし。その頃はありがたいことに仕事があったんですね。よかとピアで作品作りをするとか、ソラリアやイムズがオープンしたとか。表現する媒体も増えたから、脚本かいたり、パントマイムの舞台つくったり、作ったら出演しなきゃいけないし。
柴山:ソラリアやイムズがオープンした時は具体的に何をなさったんですか。
佐藤:ソラリアのオープンイベント。全館でいろんなパントマイマーが出現するという。2階で突然、モブがパントマイムを始める、とか。その頃まだ自分の劇場がなかったから。ビブレホールって昔あったでしょう。あそこで別役の脚本を2,3本やってます。
柴山:ビブレホールって音楽専門のホールでしたよね。あそこでは演劇は数えるほどしか上演されてないのですが、佐藤さんもなさったんですね。別役実ですか。
佐藤:そうです。多分、走りはばぁくうだと思いますよ。当時、高橋さんというマネージャーがいたんですよ、ビブレに。彼に許可をもらわなければいけなくて、ホールの貸し出しの責任者だったから。高橋氏には飛び込みで相談に言ったように記憶しています。「演劇に貸したことはない、とにかくライブでいっぱいだ」と言われて「いや、貸してくれ」と。スピーカーがドンとあって、別役やるにはちょうどいいでしょうって(説得して)。その公演を、ソラリアの深町(健二郎)さんが見に来てくれて知り合いになりました。
深町さんはちょうどソラリアオープニングの演目・キャストを探していたんです、当時ばぁくうがイベントで頑張っていた頃で、深町さんはイベント会社の人からばぁくうを紹介された。どんな事をやっているのか知りたいということで、ビブレの舞台を覗きに来た。それがきっかけでソラリアのオープニングイベントに出演することになった。
で、僕らがやったからビブレには他にも劇団が貸してくださいと行くようになった。でも確かどこかがボヤ騒ぎを起こしたんですよね、それで演劇屋には貸さない!ってことになってしまった。
柴山:JTのキャビンホールでもどこかの劇団が似たようなことをしましたね。
佐藤:そうそう。僕らはその頃ビブレを離れてキャビンホールでもしてました。
柴山:ではアトリエを持つまでは、ビブレホール、キャビンホールなどでやられていたんですね。
佐藤:それから大博多ホールね。少文(少年文化会館)とか。やりながら稽古場が大濠に移ったんですよ。1フロアーのリビングで稽古やってて、発表の場を平尾に。カラオケの撮影とかやっている会社の持ちビルがヤナセの裏にあって、4階建てのビルの2階に事務所と稽古場を用意して3階を舞台で、やってました。ビデオ制作会社。僕はそこでカラオケビデオの仕事をずいぶんもらっていたんですよね。映像の。
柴山:どこからその仕事が繋がっていたんですか。
佐藤:夢工房に入って、CМなどのタレントとして知り合って声をかけてもらって仕事をする形。だから放送劇団とは全くルートが違う。
柴山:では、その他の劇団もタレントのような仕事をしていたんでしょうか。例えば「現代劇場」さんとか。
佐藤:「現代劇場」はね、アマチュア劇団を志向していた。仕事は別でやって。「生活舞台」もね。この二つは、アマチュア劇団として存在していて、「テアトルハカタ」と「夢工房」がいわゆる職業劇団。今は境界線があいまいになって来てるから。当時はまだ左翼演劇、職場演劇などが混在していた。急速にそれが自由になっていく。今の若い演劇人たちはそういう感覚が分からない。
柴山:では何も売り込みをしなくても仕事の話が来ている時代だったということですか。
佐藤:やっぱり今の時代と同じオーディションがあった。演劇をやってるところ、モデル事務所なんかに制作が話を持っていく。そこに写真を貼ったエントリーシートを出してオーディション。
柴山:ばぁくうの団員たちもオーディションを受けていたということですか。
佐藤:向こう(クライアント)から発注があるわけです。例えば「40代の男女、20代の男女がほしい」など。それでオーディション。
柴山:劇団が代表として仕事を請け負うことができていたという意味なんですね。では、基本的に大名のアトリエだけでなくその前の時代も稽古場を持てるぐらいには稼げていたということなんですね。
佐藤:それこそ1994年から95年にかけてNHKで朝ドラ『走らんか!』をやった時に、博多の人形師が舞台だから博多弁の方言指導してほしいとか頼まれました。NHKの仕事でありがたいのはね、九州、福岡のNHKで知り合った人が、別の地域に転勤しても「佐藤さんの所に」と声をかけてくれるんですよ。そしたら結構大きな金になる。9か月間ぐらい、全部のセリフのテープ起こしからテキストレイヤーから。大きなお金を稼げたので、家賃を払うのに。
柴山:お金のシステムとしては、劇団としてお金が入った時に劇団人に給料を払っていたんですか。
佐藤:まだその頃は法人ではなかったので、外注社員として。仕事に行ってもらったら、僕らの取りが4割、その人の取りが6割。そういうシステムとして劇団運営費を出していた。有限会社にした時に提案したのは固定給で、仕事があれば金になるけど仕事がなければ全くない。不安定な額で。固定給を払うが13万~15万ぐらいしかないがそれを超えたらギャラとしてもらえる。仕事がない月でもそれが保証されるからいいだろうと思ったら、いややっぱり純粋に歩合のほうがいいというのも二人ぐらいいました。それでもいいよと。だから固定給が3人ぐらいで、ただ、経理をしてくれるから5万を上乗せしましょうとか。その頃僕は25万ぐらいもらってました。
柴山:その当時は、中野さんと佐藤さん以外には固定給をもらう3名ぐらいがいたんですね。団員だけど歩合でもらうという方が2名ぐらいいた?
佐藤:3,4人かなぁ。所属したのが他にもいろいろいたから。演劇をやらない人もいたし。タレントだけをやっているという。
柴山:では有限会社化した時に所属していたのは何人ぐらいいたんですか。
佐藤:一番多い時で15人ぐらいいたんじゃないかな。
柴山:その方たちに(全員ではないにしても)給料を払うのは大変だったと思うんですが、その当時は火星でいられたんですね。
佐藤:仕事が来た時だけの契約の人の方が圧倒的に多かったから。
柴山:本人の選択だったわけですよね。
佐藤:そうです、自分が頑張っただけお金がもらえるから。仕事が多かったですね、イベントも多かったし。ナレーションも増えていくばっかりだったし。テレビ見てたら、どんどんどんどんうちの連中がしゃべっていて。
柴山:他にはその仕事を請け負う所がなかったんですかね。
佐藤:なかった。テアトルハカタさんぐらいかな。珍しがられたというのもありましたね。うちはカネをもらうんだからと厳しかったし、それで当時の製作会社は「ばぁくうは厳しい」と知ってるわけですよ。期待されていた。
柴山:ただそういう仕事が増えると、本公演、劇団の公演が打ちにくくなりますね。
佐藤:減っていきますね。
柴山:そのジレンマはありました?
佐藤:様子を見てわかってましたね、そんなにこの仕事が長く続くわけじゃないと。だからその間、一生懸命やるだけやろうと。そしてそれを持続するためには厳しくやろうと。ただなかなかみんな集まって演劇を作っていく時間がなくなったでしょう、それを増やしていかなくてはいけないという話をした覚えがありますね。なかなか厳しい所には残っていかない…
柴山:やめていく人もいたということですか。
佐藤:そうです。生活干渉もしなきゃいけなくなるし。だから劇団の運命共同体的な体質が要求されるようになっていく。
柴山:でもそれを嫌がる人も多いでしょうし難しいですね。
佐藤:だから割と他の劇団にいたという人が来るんだけど、きびしいしタテ社会だし要求されることも高いレベルだしついていけない、ということもよくありましたね。
柴山:後発になりますがタレントが所属する劇団(会社)とかが出来ましたが、パイの取り合いにはなりませんでしたか?
佐藤:今起きてると思います。福岡でナレーション、僕が始めたのは25年位前で、その頃は演劇系でナレーションをやれる人はいなかったんです。だいたいアナウンサーやラジオのパーソナリティー上がりだった。広告代理店から見たら、僕なんかは「夢工房系」ですね。演劇をやりながらナレーションをやっている。喋りはじめたらお芝居が必要なものが増えてきた、でぼくらだけでやっていてもしょうがないのでいろんな劇団の人たち、例えばピクニックからわかれたところに所属しているガラパゴスダイナモスとか。要するに代理店みたいな状況でスタートしたけれど、演劇をやっている人たちでタレントを抱えたのが「夢工房」「テアトルハカタ」で、それを引き継いだのが「ばぁくう」という形。演劇をやっている人たちが面白いねと制作会社が知って。今、増えてるわけです。
柴山:ではタレント業…に陰りが見えてきたのはいつ頃なんですか。単価が落ちてきたとか数が減ってきたとか。
佐藤:個人の技量とパーソナリティじゃないですか。使われる使われないっていうのは。極端に声優ブームとかでやりたい人が増えてきたんですよね。そういう人たちは早く出たいから「安くてもいいです」「お弁当だけもらえればいいです」と。そして束縛を嫌うからフリーという形をとる。昔の人たちは能力があって「フリー」、今の人たちは自由が利きますフリー。だから技術的に高い人たちはそんなに要求されなくなってきてる。僕らがしゃべり始めたときは一つのラジオCМをやる時に一人何役もやったりしていた。そうやって金とっていたんです。福岡市には24,5年前はナレーターが100人ぐらいいますと言われていました。それが今は500人いると。デモテープだけで500人。今はなりたい人が多いから。1回行くと何役も用意されていたのが、今は1役のために呼ばれる。必然的に1本のギャランティーが低くなるわけですね。その分、数が増える。10年前ぐらいから急に増えました。そんなに収入がないから必然的に他に仕事をしなきゃいけない。アルバイトとして金を稼ぐ時間と、タレントとして修業しなきゃいけない時間とを一日で分けないといけない。僕らはそれがいやだったからバイト禁止してたんです。とにかくナレーション、演技に関わる勉強をしようというのが僕らの感覚だった。でも制作側の力も落ちてるし、どんどんアマチュア化していく。「アマチュアの方が面白いね」と言われたら、演技の勉強じゃない。だからアマチュア寄りの制作が多いですね。アニメの方が効率が良いわけですよね、撮影の手間がかからない。ナレーターも声優系を使えば安くなる。やってみたい人たちがいっぱいいるから。だから一気に声優養成学校の人たちに発注する…それで作れば制作費が安くなる。
柴山:では10年前から変わってきたんですね。ばぁくうが六本松から撤退したのもそういう理由ですか。
佐藤:六本松から撤退したきっかけはコロナです。あれだけの広さを維持する必要がない、能力もない、僕らが年をとってきたから集まって来る人も若い人ではない、その開拓がおろそかになる。若い子たちに合わせた教育まで手が回らない、知恵が回らない。僕らがやって来たことを信じるしかないからそれを要求してしまう。そうするとだんだん人がいなくなり、そうすると仕事も減っていき、ストレートに収入が減る。僕だけが稼ぐしかなくなるし、僕も減っていく。
柴山:場所を貸すということはなさらなかったんですか。他の劇団も発表の場として使っていいよと。夢工房さんはそうなさっていたと思うんですが。

佐藤:消防法で難しいんですよね。自分たちが使う分にはいいんですけど、許可が必要になるんです。夢工房もそんなことしてなかった。潜りでやれないことはないんですけど、法律的には貸し小屋業はできない。背に腹は代えられないし、どうしてもここでやりたいという劇団には貸しましたよ。劇団ぎゃ。ですね。2005年に地震があったでしょう、あの時に「劇団ぎゃ。」に貸す予約も入れていたんですけど、地震でひびが入ったんです。だからキャンセルにした。芝居が出来なくなって、2005年から2009年ぐらいまでは稽古場としてくすぶってはいたんですけど、2009年に六本松に開きました。

柴山:そしてコロナの影響もあり、2023年に六本松のアトリエを閉めたんですね。…今回は六本松にアトリエを開くまでのお話でしたが、長い演劇人生を語っていただき、今日はありがとうございました。