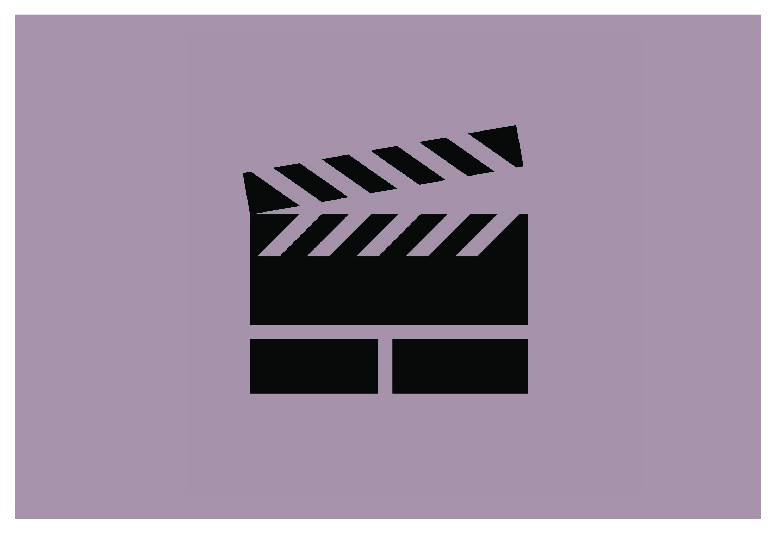企画:マレビトの会
作品と監督:『しるしのない窓へ』(三間旭浩監督)、『ヒロエさんと広島を上演する』(山田咲監督)、『夢の涯てまで』(草野なつか監督)、『それがどこであっても』(遠藤幹大監督)
*Asian Film Joint 2024の一作品として、シネラ(福岡市総合図書館 映像ホール・シネラ)にて上映された。
感想
マレビトの会は、松田正隆を代表として2003年に舞台芸術の可能性を模索するために設立された演劇カンパニーである。被爆都市である広島や長崎をテーマとした作品を作り続けており、既存の上演形式にとどまらず様々な演劇表現の可能性を追求してきている。今回上映されたのは、2013年から取り組んできた「~を上演する」シリーズの3作品目。一つの都市を複数の作家が訪れて戯曲を書き作品を上演する形態で、これまでに『長崎を上演する』(2013-2016)、『福島を上演する』(2016-2018)が作られてきた。本作はそれらと形態が異なり、舞台公演ではなく映画である。4人の作家が広島に赴き、滞在して広島を感じ、考えたことを、4本の短編映像にしている。
私は松田正隆の演劇作品は観ているが、この『~を上演する』シリーズは実はこれが初めてである。従って前二作の舞台(演劇)と今回の映像とで表現手法を変えたことが何を意味するのか、比較する事ができない。演劇の場合は、どれだけ「直接的」に描こうとも、ワンクッション挟んだような、「フィクションとしてのリアリズム」にならざるを得ない。それは舞台上のリアル(上演している現実)が時間的空間的には「本当ではないこと」を実感させるからだが、逆にそこに舞台表現の面白さ、奥深さ、可能性がある。他方で映像は、少なくとも空間としては現場を撮影する事もできるし、カメラのおかげで観客の視点を誘導しやすい。そのためリアルな没入感を与えることも可能だ。舞台作品として作られてきたシリーズが3本目にして映画になるという変化、その違いを見比べたうえで本作を味わえなかったのが、私は悔しい。
さて、本作は『しるしのない窓へ』(三間旭浩監督)、『ヒロエさんと広島を上演する』(山田咲監督)、『夢の涯てまで』(草野なつか監督)、『それがどこであっても』(遠藤幹大監督)の4本から構成されていた。私が面白く感じたのは、『しるしのない窓へ』と『それがどこであっても』である。
『しるしのない窓へ』は、広島に住む若い夫婦と女子大生が登場する静かな物語である。若い夫婦はともに物を作っている。夫は洋服を(誕生日には妻に手製の服をプレゼントする)、妻は詩を。妻は女子大生と詩を共作しているのだが、その詩と大きな静かな川が、本作の中心をゆったりと流れている。
詩は、川に映った窓について語り始める。実際には閉まっているアパートの窓だが、川に映ったそれは開いていて…そこに住む人がピーナツを剥いていて…そう紡がれる言葉たちに、川に映った「もう一つの世界」に想いを馳せる。なぜなら、その川こそが、80年前の惨状もその後の変遷も、黙って静かに見てきたであろうから。詩に詠われた「川に映る開いている窓」とは、「あの8月6日に消えてしまった、あるはずだった幸せな風景」なのかもしれないと思ったから。流れゆく水は時の象徴でもあるけれど、川面に映るものは決して流れて消えない――私たちの記憶に刻印されたあの朝のように。
詩の交換を終え一旦別れた後に妻は女子大生に呼び止められる。その時の、「何を言えばいいのか忘れました」のセリフと共に、女子大生の後ろに映る原爆ドーム――このショットは多少あざとい気もしたけれど、後から、彼女のセリフの意味を考えて――「何を言っていいのか言葉を失う」ということなのか、「風化し忘れかけている現状」を指しているのか、あるいは「記憶を封印することにした社会」を揶揄しているのか、解釈を観客の手に委ねた気がした。
ラスト、完成した詩の朗読が続く中、夫婦の小さな部屋から夫の姿が消え、やがて妻の姿が消え、女子大生が現れて彼女の白い手の甲に光が当たって映画は終わる。個々人が生まれて消えてをくり返してきた人類の営み。その儚さと尊さを示唆して、映画は静かに幕を下ろした。
『それがどこであっても』が興味深かった理由は、「体験しえぬものを私たちは如何にして受け止めていくのか」について考えさせられたからである。冒頭において、松田正隆が劇団員にマイムについて語る舞台稽古のシーンがある。メモを取っていないのが悔やまれるが、松田はその中で、俳優と観客が「まさぐりあう」という表現をする。演技(マイム)の話ではあるが、私たちは常に、他者とズレながら互いに手を伸ばして「まさぐり合い」ながら理解をしていかざるを得ないのだと言われた気がしたのだ。他者の経験をどう理解できるのか、過去の記憶をどう受け止められるのか、過ぎ去った時間をどうやって感じることができるのか。「追体験」といった軽い言葉でなく、しかし一方的に無理だと諦めるのでもなく、時間的・空間的に離れていても「まさぐりあう」ことで理解へと近づけるはずだという健全な意識。それはナガサキにもヒロシマにもフクシマにも(時間的・空間的に)距離のある者が試みるべきことであり、まさにマレビトの会の『~を上演する』シリーズの試みである。
後半は、一転して音響スタッフである青年が街に出て音を拾うシーンが最後まで続く。彼の持つマイクは、黒色の顔の形をしている(モアイ像にも似ている)。彼はそのマイクで、電車の音、河川敷の風やざわめく草の音、公園での子どもたちの声を拾って歩き続ける。やがて彼は、いささか暴力的に、その人間型マイクをひきずったりコンクリートの壁にこすりつけたり宙づりにしたりして音を拾いはじめるのだが、いつしかその荒々しい音が、あの日のヒロシマの音であるかのように聞こえてくる。思わず唾をごくりと飲んだ。彼が意図しているのかいないのかその淡々とした表情からは読み取れないけれど、まさしく彼のやっていることは、タイトル通り「それがどこであっても」、「まさぐり合って」記憶や経験に近づこうとする行為なのだ。
『~を上演する』シリーズは、おそらく、その土地との距離をめぐる作品だろう。物理的な距離にとどまらず、さまざまな意味での距離。それは表現する作家たちのみならず、観客にとっても同じだ。本作を見て、私とヒロシマの距離について考え、近づこうとし、少なくとも一歩近づいた気がしている。「まさぐっていく」こととは、きっとそういうことなのだろう。